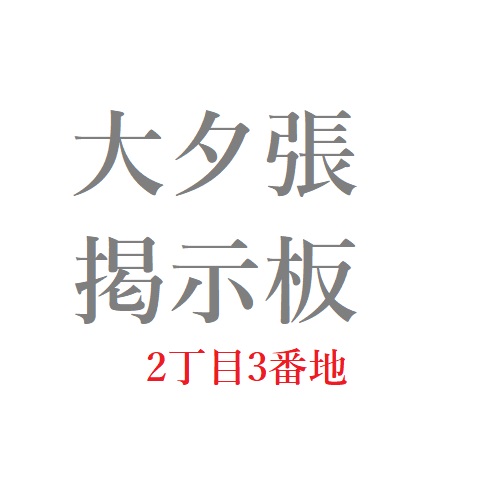希 望|夕輝文敏

十一月の冷たい雨が、歩道に散った落ち葉を濡らしていた。人通りの絶えた日曜日の夜、雨音だけが、シャッターを閉めた商店街を駆け抜けて行く。
眠りにつこうとしている通りの中、一軒の寿司屋には、まだ明りがついていた。
だが、暖簾は外されていた。
丸万寿しの大将、山越信明は、最後にもう一度と、長年使い込まれたカウンターを拭いていた。
「あんた、今夜はもう、これぐらいで、ねぇ。後は、私がやるから」
傍らで、妻の恵美子が労わるように言った。
「ああ、そうだな」
信明は、カウンターを見渡すと、名残り惜しそうに言った。
信明が三一才のときに、中の島通のこの場所に、丸万寿しを構えた。それから三〇年、妻と二人で、客に支えられながら、大切に築いて来た店であった。
「まさか、こんな形で、店を閉めるとは思わなかったわねぇ」
恵美子は、店の中に置かれた暖簾を見ながら、溜息をつくように言った。
「そうだなあ。三〇年もやってきたのになあ・・・」
信明は夏頃から、足の付け根のしこりが気になって、先月病院へ行ってみた。痛みは全くなかったのに、すぐに入院検査が必要だと言われた。一抹の不安を抱えながらも、大したことはないだろうと思っていた。
だが、検査の結果は、リンパ腫であった。信明は、恵美子と二人で、医者の話を聞いていた。
話を聞き終わると、恵美子は泣崩れてしまった。
今まで信明を支え、気丈に店を切り盛りしてきた恵美子であったが
「先生、治るんですよね」
と正気を失ったように、医者に詰め寄った。
信明は、そんな恵美子の姿を初めて見た。そして、自分の前に突きつけられた現実の深刻さを、どう受け留めて良いのやら、不安を感じていた。
医者は、幸い薬の効きやすい部位のため、時間はかかるものの、完治できる可能性も高いことを話した。
信明は、医者の話を聞きながら、ふと窓の外を見た。そこには、手稲山の稜線が姿を現していた。
そして、一瞬、生まれ育った炭鉱街の山並みを思い浮かべた。
いつも自分たちを見守ってくれた、夕張岳の姿であった。
その日から、信明は店のことばかり考えていた。
だが、いくら考えても、店を続ける術は見出せなかった。
「やはり、店は閉めるしかないか」
信明は、消灯時間の過ぎたベッドの上で、天井を見ながらつぶやいた。
翌日、信明と恵美子は、丸万寿しを閉めることを決めた。
「あの医者も、全く融通がきかないなあ。こっちは、三十年も続けてきた店を、閉めるって言うのに、たった三日しか、外泊許可が出ないんだからなあ、全く」
何もかもが、急な話であった。
人生の節目が、一遍に折り重なったようであった。
長年世話になった客には、落ち着いたら礼状で、挨拶をさせてもらおうと思い、改めて閉店については、知らせていなかった。何よりも、こんな急な形で店を閉めることが、二人とも心苦しく思っていた。
それでも、何人かの馴染みの客が、信明を心配して、店を訪ねて来てくれた。その中には、ここ十年ばかり、家族で来てくれた山本もいた。
山本のところには、小学生の男の子と女の子がいた。この十年、信明たちは、二人の子供達の成長を、自分たちの子供の幼児期と姿を重ね、見守ってきた。
子供達が来ると、恵美子はお菓子を渡したりしていた。子供達も、おもちゃ持参で、丸万のおじさん、おばさんに会うのを楽しみにしていた。
信明も恵美子も、この三〇年客筋で苦労したことはなかった。
一度子供連れの客が来てくれると、ずっとその子たちの成長を見ることができたのも、幸せなことであった。
「この店は、お客さんには、本当に恵まれていましたね。そして、大家さんにもねえ。本当に、ありがたいですね・・・」
「そうだなあ。特に、大家さんには、最後の最後まで、世話になりっぱなしで」
外泊許可が出ると、信明と恵美子は真直ぐに、大家を訪ねた。
「永い間お世話になって、急な話で申し訳ないんですが、店を閉めることになって・・・」
大家は驚きながらも黙って、信明と恵美子の話を聞いていた。
そして聞き終わると
「丸万さん、私もちょうど今の建物も古くなってきたし、立て替えようかと思っていたところなんですよ。これから雪が降るし、春になって雪が溶ける頃までは、工事にかかれないから、それまで、荷物を置いたままで、どうぞ使ってやってください。もちろん、家賃はいりませんよ。いや、むしろ、最後まで丸万さんに使ってもらった方が、私も嬉しいですから。だから、まずは体のことを第一に考えて、ねえ・・・」
信明は、大家の心遣いが心底ありがたかった。
「ありがとうございます」 と言うのがやっとで、二人はいつまでも頭を下げていた。
「店の中は、こんなもんでとりあえず良いだろう。後は済まないが、春まで頼むな」
信明は厨房道具も少なくなり、ガランとした店を見渡しながら言った。
「任せておいて。春までなら、全部きれいにかたづくわ。それに、来週は啓子も来てくれるって言うし・・・」
信明は、娘の啓子には、もうしばらく、知らせないようにと言ってあった。
啓子は昨年結婚したばかりで、今は五ヶ月の身重であった。恵美子は、信明の気持もわかりながらも、一人では抱えきれず、嫁ぎ先の仙台に電話をした。
「もしもし、お母さん、もしもし、どうしたの、お母さん」
啓子は、冷静さを失った恵美子の電話に戸惑いを感じた。
「啓子、お店閉めることになって、お父さんが、お父さんが大変なの・・・」
啓子は、母の話を聞くと、すぐに夫に相談し、札幌へ帰ることを決めた。
啓子は、ふっと思い出した。
以前にも、こんな母を見たことがあった。
弟の健一が、死んだときであった。
あの日、啓子は友達の家に遊びに行っていた。あのときも、母から急を知らせる電話がかかってきた。
父のことも思い出した。あんなに野球が好きだったのに、健一が死んでからは、客が帰ると、すぐにテレビのチャンネルを変え、野球を見なくなっていた。
(今度は、お父さんが・・・)
啓子は、そんなことがあるはずがないと、自分の恐れを打ち消した。
「後は、外の物置見てくるわね」
恵美子は、勝手口の戸を開け、外に出た。
いつのまにか、雨は上がっていた。
物置には、家の中に入りきらない家庭用品も入っていた。その中には、子供達のおもちゃなどもあった。
今は、子供に新しい物を買い与える時代になったが、信明も美啓子も、親の苦労を見ながら育ったので、どんな物でも、簡単に捨てることができなかった。
恵美子は、古い木の箱を運び出してきた。
「その箱、俺がこさえた子供たちの・・・」
信明は、二五のときに恵美子と結婚し、翌年長女の啓子が生まれた。
そして、二年後には長男の健一が生まれた。
当時住んでいた狭いアパートは、いつも子供たちのおもちゃが散らかっていた。それを見かねた信明は、二段式の引出しがついた木のおもちゃ箱を作った。
「あの子達が、まだ小さい頃、あなたが作ったのよね。何か懐かしいわ・・・」
恵美子はそう言いながら、雑巾で箱を拭き始めた。そして、汚れを取ると、上の段の引出しを開けた。
そこには、啓子が小学生の頃、遊んでいた着せ替え人形が入っていた。
「あら、これ啓子のお気に入りの人形だわ。着せ替えの服も一緒になって」
恵美子は、人形を手に取ると、優しく髪の毛を撫ぜていた。
恵美子は、小樽の貧しい漁師の家に生まれた。兄弟が五人もいて、生活が大変であった。子供の頃、新しいおもちゃを手にしたことは、一度もなかった。
恵美子にとって、新しい人形は、宝物のようであった。だから、娘の成長に伴い使わなくなった着せ替え人形などは、大切にしまっておいた。
そして、店に来る子供連れの客があると、それらのおもちゃで遊ばしたり、ときには使ってもらったりしていた。
「そうだ、この人形、まだきれいだもの、山本さんとこの瑞穂ちゃんに、使ってもらえないかしら」
恵美子は声を弾ませて言った。
「そうだなあ。山本さんとこなら、喜んで使ってもらえるだろなあ。でも、今はだめだ。かえって、山本さんに、負担かけてしまう」
信明はそう言うと、人形から目を離した。
「そうですね。今は、まずいですよね・・・」
恵美子は、少しうつむき加減で言うと、人形を引き出しの中に戻した。
そして、次は下の引出しを開けてみた。
そこにも、啓子のおもちゃばかりであった。
少しだけ手にとってはまた戻し、引き出しを締めようとしたが、何かに引っかかったようで、閉めることができなかった。
「あら、どうしたのかしら」
何度試しても、上手く行かなかった。
「もう、古いから建付けが悪いんだろう。どら、貸してみれ」
信明は、恵美子の側へ行くと、勢い良く引出しを引いてみた。
すると、引出しは一気に抜けて、中のおもちゃが、床にこぼれ落ちた。そして、引出しの奥からは、子供用の小さなグローブが出てきた。色褪せた緑色のグローブであった。
「あっ、このグローブ・・・」
傍らで恵美子は、悲鳴に似た声を上げた。
「そうだ。健一のグローブだ」
信明は、僅か五才で逝った息子を、抱き上げるかのように、グローブを手に取った。
「こんなときに、出て来やがって、全く健一の奴は・・・」
長女の啓子を授かった二年後に、健一が生まれた。夫婦にとっては、宝物のような子供達であった。
長女の啓子が小学校に上がると、健一も幼稚園に入った。
その頃、健一は父親の影響もあり、野球に興味を持って、グローブを欲しがった。信明は幼児用の小さなグローブと、ゴムまりのボールを健一に買い与えた。
信明の父も野球が好きで、良くキャッチボールをして遊んでくれた。もし、炭鉱事故さえなければ、孫の健一とキャッチボールを楽しむこともできたのにと、信明は思うことがあった。
丸万寿しは、毎月第二、第四月曜日が定休日であった。月曜の休みになると、健一は幼稚園へ行く前から、キャッチボールを楽しみにしていた。
そんなある日、いつものように、中の島公園でキャッチボールをしていると
「お父さん、僕、小学校のお兄ちゃん達が使っている、イボイボのついたボールがいいなあ・・・」
と健一は、ねだった。
信明は少し考えてから
「そうだなあ、小学校に入って野球部に入るなら、今から慣れておいたほうが良いか」
と言った。
その夜、商店街の寄合の帰り、信明は軟式ボールを買って来て、寝ている健一の枕元に置いた。
「わあ、お父さん、お母さん、お姉ちゃん、イボイボボールだ」
健一は、朝早く目覚めると、はしゃぎながら言った。
「健一は、店が休みの日になると、もう幼稚園行く前から、お父さん、帰ってきたらキャッチボールだよって、良く言っていたわね」
信明が手にした小さなグローブを見ながら、恵美子は言った。
「そうだなあ。でもなあ、本当は、俺の方が楽しみでなあ」
信明は、一緒にキャッチボールをしているときの、健一の嬉しそうな笑顔を思い浮かべていた。
店がある日は、啓子も健一も、小学校、幼稚園が終わると、真直ぐ店に帰ってきた。
夏も終り、秋の気配が漂い出した頃には、健一は、かなり早い玉も投げられるようになっていた。そんな九月のある日、健一は幼稚園から帰ってくると、いつもになく信明にまとわりついていた。
「ねぇ、お父さん、キャッチボールしようよ。ねぇてばぁ」
信明も夕方前に暇になったら、一緒に遊んでやろうと思っていたが、その日に限って、客足は絶えなかった。
健一も待ちきれずに、何度も信明にねだるのであった。
「お父さん、まだ・・・」
信明は不憫に思いながらも、つい叱ってしまった。すると、健一は店の外へ出て行った。そして、一人で店の裏の壁にボールをぶつけながら遊び始めた。
心配して、恵美子も様子を見に行ったが、車の通りのない裏で遊んでいるのを見届けると、店に戻って来た。
それからしばらくして、店の前でけたたましい車のブレーキの音と、同時にドーンという鈍い音が聞こえてきた。
最初に恵美子が、店の外に飛び出して行った。
「健一、お父さん、健一が・・・」
恵美子の叫び声が、通りに響いた。
信明もあわてて駆けつけると、健一は頭から沢山の血を流し、道路の端に倒れていた。
健一の手には、ボールが握り締められていた。健一はボールを追いかけ、通りに飛び出し、車に撥ねられてしまった。
血だらけの健一を見て、友達の家から駈けつけて来た啓子は
「お母さん、健ちゃん死んじゃったの。お父さん、健ちゃん、死んじゃったの」
と言うなり泣きじゃくり出した。
「そんな訳ないだろう、健一が、健一がこんなことで、こんなことで・・・」
信明は、自分に言い聞かすように、大きな声で言った。
健一は、ほぼ即死状態であった。たった五年間の短い一生であった。
信明は、健一の死を心から悔やんだ。あのとき、一緒に遊んでやれなかった自分自身を責め続けた。そして
「あいつは、本当に良い息子だった。俺にはもったいないぐらい良い息子だった」
と、仏壇の前で呟く日々が続いていた。
そんな信明が、健一の死を受け入れるまでは、長い時間がかかった。そして、やっと受け入れた頃、健一の存在 を身近に感じることが、多くなっていた。
「もし、あの子が生きていたら、この店閉めなくても良かったかもしれないのにね。だって、あの子、大きくなったら、お父さんみたく、寿司屋さんになりたいって・・・」
恵美子は、こぼれ落ちたおもちゃを拾いながら言った。
「そんなこと言うもんじゃない。健一が聞いていたら、悲しむじゃないか」
信明は、恵美子を嗜めながら、自分にも同じ思いがあることに気づき、後ろめたさを感じていた。
信明の人生には、不幸な出来事が、多かった。中学一年のときに、落盤事故で父を亡くしてしまった。それから、下の三人の弟、妹たちの面倒を見ながら、母親を支えてきた。
中学を卒業すると、薄野の大きな寿司屋に住み込みで働いた。寿司屋を選んだのは、口にすることもできなかった寿司を、母親や弟達に、腹一杯食べさせてやりたいと思ったからだった。
そして、生前父が酒を飲んだとき
「今度、銭入ったら、皆で鉄ちゃん寿司に行ってみたいなあ」
と言った言葉が、信明の心に強く残っていた。
一緒に、三人の見習いが入ったが、一年後には、信明を除き皆辞めてしまった。職人の世界は、想像以上に厳しいものであった。
それから、二年が経った頃、親方が信明に言った。
「良く辛抱して、三年もったなあ。おまえは、一度も辞めようとは思わなかったのか」
「はい、あの、いいえ」
と信明がはっきりと言わないと
「何も、ここまでもったんだから、正直に言ってみろ」
親方は少し酒臭い息をしながら、優しく言った。
「俺、ここ辞めると、母さんに心配かけるから。俺とこ、父さんいないし、下にまだ三人もいるし。それに・・・」
信明はそこで言葉を、飲みこんでしまった。
「それに、何だ。今日は全部喋ってみれ」
親方は信明の言葉を待っていた。
「それに、俺とこ貧乏だったから、母さん達に腹一杯寿司食べさせてやるの夢なんだ・・・だから、早く一人前になって、母さんにも楽させてやりたいと思って・・・」
信明は下を見ながら、少しはにかんで親方に言った。
親方は、信明の坊主頭を撫ぜると
「そしたら、明日から、俺がみっちり仕込んでやるからなあ」
と言ってくれた。
それから、更に七年の修業を経て、信明は二五才のときには、カウンターに立つことができた。そして、三一才には、独立して店を持つことができた。
今の丸万寿しは、親方が世話をしてくれた店であった。信明の人生でも、最も輝いている時期であった。
それから、僅か二年後に、長男の健一を亡くしてしまった。早くに父を亡くし、かけがえのない息子も、幼くして失ってしまった。
そして、今度は自分の病気により、店までも閉めることになってしまった。
「恵美子・・・」
「うん、何・・・」
恵美子は、振り向きながら言った。
「俺は、十三のときに親父を亡くし、三十三のときには、健一も亡くしてしまった。あのときは、こんなことってあるものかとも思っていた。でもな、今は、俺は幸せ者だと思っている。こうして親方の世話で店持てて、お客さんにも恵まれて。だから、俺はちっとも、自分のことを不幸だと思っていない。俺は、本当に幸せ者だ。だから、おまえにも、心からお礼を言いたくて。本当に、今までありがとうなあ。俺は、おまえに、とても感謝している。なのに、こんな形で店閉めることになって、本当に、済まない・・・」
信明はそう言うと、妻に深々と頭を下げた。
その夜、家に帰ると、信明は妻が作った夜食を肴に、久し振りに酒を飲んだ。酒を飲みながら、三〇年分の疲れが、一気に被さってくるのを感じた。そして遠ざかる意識の中に、前岳に被さった夕張岳の姿と、長屋がびっしりと張り付いた故郷の街並みが、薄っすらと浮かんできた。
(ああ、帰りたいな・・・あの頃に)
そう呟くと、信明は深い眠りへと落ちて行った。
「お父さん、お父さん、起きてよ」
懐かしい声がして目を開けると、傍らに健一が立っていた。
信明は店の小上がりに寝ていた。店の中を見渡すと、厨房には沢山の器が並べられ、カウンターの冷蔵庫にも、色艶の良い寿しネタが所狭しと置かれていた。
「健一、おまえどうしてここに・・・」
信明は驚きながらも、嬉しさが込み上げてきた。
「だって、お父さん、お客さんが帰ったら、一緒にキャッチボールしてくれるって、約束したしょ」
良く見ると、健一の左手には、あの緑色のグローブがあった。そして、左手には信明のグローブを持っていた。
「ああ、そうだったなあ」
信明は起きあがると、健一からグローブを受け取った。
「えぇと、ボールは」
と信明が言うと
「お父さんと一緒に遊べるようにって、お姉ちゃんが、秘密の場所に置いてくれたんだよ。僕、その場所知っているよ」
健一はそう言うと、店の看板の前に立った。
「お父さん、暗いから看板に電気つけて」
「あ、待ってな」
信明は、カウンターの横にあるスイッチを入れた。
すると看板に明かりがつき、丸万寿しの文字が、闇の中にくっきりと浮かび上がった。通りは街路灯が灯っていたが、車も人通りもなかった。
健一は、看板の下にある小さな穴に手を入れると、ハンカチに包まれたボールを探し出した。
「ほらね、ちゃんとあったでしょう」
健一は嬉しそうに言うと、信明と手をつないだ。小さな手の感触が懐かしかった。
二人は、いつも遊んでいた中の島公園へと、歩き出した。
信明は、健一の手を握りながら、体中に幸せが満ちてくるのを感じていた。
信明は、啓子からも、健一からも、そして、妻からも沢山の幸せを貰って、今まで生きてきた。この家族にめぐり合えて、本当に良かったと思った。そう思うと信明は、たまらなくなって、健一の手をぎゅっと握り締めた。すると、健一も握り返してきた。
「お父さん、やっと、キャッチボールができるね」
健一は、嬉しそうに、あのイボイボボールを握っていた。
「これから、お店の休み月曜でなく、日曜にしようか」
「えっ、本当。だったら幼稚園も休みだから、お父さんと一杯キャッチボールできるよね」
健一は嬉しそうに言った。
信明は、健一の嬉しそうな顔を見ているうちに、切なくなってきた。あのとき、一緒に遊んでやれば、健一だってあんなことに・・・。信明は、心の中で、何度も健一に詫びていた。
公園に着くと、街路灯の下に恵美子が立っていた。
「お前も来たのか・・・」
信明が言うと
「お母さんだけ、仲間外れじゃ可愛そうだから、僕がお願いして来てもらったんだよ」
健一は、恵美子の手を取りながら言った。恵美子も嬉しそうに、健一を見ていた。
「あれ、健一、そのイボイボボールどうしたの」
恵美子はそのボールのことを、良く覚えていた。
「秘密の場所で見つけたんだよ、ねえ、お父さん」
健一は、少し悪戯っぽい笑顔を浮かべ言った。
恵美子が見守る中、誰もいない夜の公園で、二人はキャッチボールを始めた。
信明も恵美子も、健一の一つ一つの動きを、目を細めて見ていた。それは、とても幸せな陽炎のようなときであった。この切なくて、満たされた瞬間が、いつまでも続けばと、思わずにはいられなかった。
しばらくすると、信明は疲れを感じた。どうしようもなく体が重く、立っているのもやっとであった。信明が、しゃがみ込んでしまうと、健一と恵美子が駆け寄ってきた。
「お父さん、病気なんだって」
健一は心配そうに、信明の顔を覗きこみながら言った。
「いや、たいしたことないから」
信明は、健一に心配かけまいと、微笑みながら言った。
健一は、そんな信明の顔を、悲しそうに見ながら言った。
「お父さん、幾つになったの」
「お父さんか、今年の九月で、六一になった」
それは信明自身も驚くほど、疲れた声であった。
健一は、少し戸惑いながら言った。
「お父さん、僕、五才のままなんだ。あのときから、ずっと、五才のままなんだ」
それは、とても悲しそうな声であった。
「お父さん、丸万寿し止めちゃうの」
「うん、病気治るまで、少し時間かかるって、先生に言われたから・・・」
信明は、努めて元気そうに言った。
「僕のせいだね。僕がちゃんと大きくなっていたら、お父さんの店継いでいたのに。あんなことになって、僕はいつまでも、五才のままだから・・・」
健一はそう言うと、ポツリと握り締めたボールの上に涙をこぼした。
「健一のせいじゃないよ。かえって、お父さんこそ、あのとき、一緒に遊んでやれなくて、本当に済まないと思っている」
「そんなことないよ。お父さん仕事忙しいのに、いつも時間作って、一緒に遊んでくれたしょ。それに、僕、ちっとも寂しくないよ。いつだって、お母さんやお姉ちゃんも、僕のこと忘れないで、思っていてくれるし。ただ、お店がなくなるのは、悲しいな・・・」
信明は、思わず健一を抱き寄せた。
「おまえ、そんなにお父さんが、店閉めてしまうのが、悲しいのか」
「うん、だって、丸万寿しは、家族の一員だもの。あそこで、僕も、お姉ちゃんも、楽しいこと一杯あったし。それに、僕お父さんのお寿司、大好きだったし。だから、お父さん・・・」
健一は、信明の腕の中で、甘えるように言った。
「健一、ありがとうな。お父さん、おまえにそう言ってもらえて、本当に嬉しいよ。ありがとうな・・・」
信明は、声を詰らせて言った。傍らでは、恵美子も泣いていた。長い間、三人はそうしていた。
やがて、健一は、砂が指の間から、こぼれ落ちるように、信明の腕から静かにすり抜け、信明と恵美子の間に立った。
「お父さんの病気、必ず治るよ。だから、丸万止めちゃいやだよ。あの店があれば、またお父さんと一緒に、キャッチボールもできるし・・・」
健一の輪郭は、徐々に消えかかってきた。
「健一、行くな、健一・・・」
信明は思わず手を伸ばして叫んだ。でも、その半透明な体は、もう信明の腕では、抱きしめることはできなかった。
「お父さん、今日は、キャッチボールしてくれてありがとう。お母さんも、一緒に公園に来てくれてありがとう」
健一は、笑顔で手を振った。やがて、健一の姿は完全に消えてしまった。
「健一、健一・・・」
信明は、健一を呼ぶ自分の大きな声で、目が覚めた。そして、恵美子も、布団から起き上がった。
二人は同時に
「健一が・・・」
と声を出した。
二人は、同じ夢を見ていたのであった。
「よし、店へ行こう」
二人は、素早く着替えると車に乗り、丸万寿しへと向かった。
夜の闇も開け、薄っすらと空が明るくなっていた。店に着くなり、信明は、看板の下から手を入れた。そして、ハンカチに包まれたボールを取り出した。
「あっ、やっぱりあった。健一のイボイボボールだ」
信明は、ハンカチを取ると、しっかりとボールを握り締めた。
「このボール、啓子が、あのとき、ここに置いたのね」
恵美子は覚えていた。
葬儀が終った後、健一の荷物を整理していると、ボールが出てきた。
信明は、見てるだけでも辛いので
「そんなの捨ててしまえ」
と言ったが、小学校一年の啓子は、頑として聞き入れなかった。
「捨てちゃダメ。これ、健ちゃんの大事なものだから」
と言って、どこかへ持ち去ったのであった。
あれから、二十八年の歳月が流れた。
信明は、ボールを握り締めながら言った。
「恵美子、朝になったら、大家さんの所へ行こう。そして、頼むんだ。もう一度、この場所を、丸万寿しに貸してもらえるように」
「そうですね。丸万寿しは、私たちの、健一の、大切な家族なんだから。それに、健一も、また、キャッチボールがしたいだろうから・・・」
恵美子も頷くように言った。
やがて、朝日が昇り、丸万寿しの看板を照らし出した。信明と恵美子は、光の中に浮かび上がった、丸万寿しの文字をしっかりと見ていた。
そして、信明は光の中に、前岳に被さった夕張岳を見たような気がした。
(こんなことで、負けてたまるか。こんなことで・・・)
信明は、故郷の山並みに向かって、そう心の中で呟いた。
(2007年 発表)
(作者紹介)
夕張市鹿島生まれ
生まれてから高校卒業までの18年間を大夕張で過ごす。『ふるさと大夕張』にはしばしば投稿していたようだが、素顔は謎である。札幌在住。