路面電車に揺られて|夕輝文敏

路面電車に、少し疲れた心を乗せると、路面電車は、優しく包み込んでくれるかもしれない。年の瀬も迫ったクリスマスの夜、私はそんな路面電車に出会った。
その夜、私は一人ぽつりとグラスを傾け、店の窓から路面電車を眺めていた。
電車の車窓の向こうには、昨夜の食卓テーブルが見えてくる。クリスマスイブの食事が、四人分用意され、真中には、大きなケーキが置かれている。妻と私は、時計を見ながら座っていた。
その夜、二人の娘たちは遅く帰ってきた。仕事、友達との約束が、いつの間にか優先事項になっていた。これは、どこの家庭にでもあることで、特別なことではないのかもしれない。ただ、私たちは、まだ慣れていなかった。
私は、グラスのウイスキーを飲み干すと、お代わりを頼んだ。そして、ポケットに手を入れ、キーホルダーを取り出す。
昨夜、妻からプレゼントされたものだ。キーホルダーをカウンターに置くと、ウイスキーを一口飲んだ。少し心が暖かくなる。
妻と初めて出会ったのも、ちょうど今頃の季節であった。港町の洒落たレストランで、食事をしながらクリスマスイブを、二人で過ごしたことがあった。もう、二十数年前のことであったが、ふと思い出した。
グラスを空けると、私は店を出た。
街は、イルミネーションに包まれていた。白く積もった雪に、それらの光が反射し、通りは、灯りに満ちていた。灯りの中を、人々が歩いて行く。
それぞれの人にとって、今年はどんな一年であったのだろう。心の中は見えないが、灯りに包まれている人々は、幸せそうに見える。そのことに、ホットしたものを感じながら、私は電停に向かって歩き出した。
私にとっては、この一年は厳しいものであった。人は減らされ、仕事はきつくなってきている。この不景気で給料、ボーナスも削られ、職場には不満が満ちていた。それらの不満を一手に受け、業績を伸ばすために、無理を重ねてきた。
私は急に、今年一年の疲れを感じてきた。少し重く感じ始めた足で、西四丁目から、すすきの行きの路面電車に乗った。
まだ、九時を過ぎたばかりで、電車は空いていた。私は入口近くの座席に座った。向こう側の窓には、色取り取りの電球に輝くクリスマスツリーが見える。
妻も今夜は職場の忘年会で、この辺りで飲んでいるはずだ。
「クリスマスの日に忘年会なんって、まったく」
と言いながら、結局欠席する訳にもいかず、今夜は薄野にいる。
電車は、光の中をゆっくりと動き出す。ふと娘二人と、ここから終点まで電車に乗ったことを思い出した。あの頃、二人はまだ小学校の低学年であった。ちょうど、今のマンションに越してきた年の夏であった。
「お父さん、電車に乗りたい」
と下の子が言い出すと
「私も始まりから終わりまで乗ってみたい」
と上の子も言った。
地下鉄と違い外の景色が見える分、路面電車は子供たちにとっては、新しい世界であった。およそ五〇分、電車に揺られて、私たちは車窓に広がる景色を楽しんだ。あれから何年経ったのだろうか。新しい世界も、今では日常の風景の一部になっていた。あれ以来、終点まで電車に乗ったことはなかった。
そんなことを思い出しているうちに、電車は西線六条の電停に差し掛かってきた。そのとき、路地の奥に、古い木造の建物が見えてきた。それは、かつて子供の頃暮らしていた、炭鉱長屋に似ているような気がしてきた。私は、急にその建物を確かめたくなり、電車を降りた。
近くで見ると一軒家ではあったが、作りは炭住そのものに見えた。今どき、良くこんな建物が残っていたと、感心するほどであった。
建物の前には、大きな赤提灯があり「居酒屋」と書かれていた。だが、店の名前はなかった。私は一瞬ためらったが、思い切って店の戸を開けた。
中に入ってみると、客は誰もいなかった。戸を閉めると
「いらっしゃいませ」と声がした。
奥から紺の絣を着た、四十を少し過ぎたぐらいの女将が出てきた。
奥といっても、六人ぐらいがやっとの、カウンターだけの小さな店であった。そのカウンターの左横に、居宅らしい奥が見えていた。
私は、入口近くの椅子に座った。
「良かった。今夜初めてのお客さんが来てくれて」
と女将は嬉しそうに言うと、湯気の立ったお絞りを取り出した。
「今夜初めての客かい。クリスマスなのに、それは淋しいね」
と私はお絞りを受け取ろうとした。
「熱いから、気をつけてね」
と女将は渡してくれた。
私は「大丈夫だよ」と言いながらお絞りを手に取った。
すると、あまりの熱さに「あっち」と言って、おしぼりをカウンターに落としてしまった。
「だから、言ったでしょう」
と女将は笑いながら言った。
まるで、私を子ども扱いしているようで失礼だと思ったが、女将の笑い顔を見ているうちに、何故だか、懐かしい気持ちになってきた。女将だけではなく、この建物全体が懐かしく感じられた。
私がおしぼりで手を拭き終わると
「外は寒かったでしょう。もっとストーブの側に来たら」
と女将は言った。
私は、促されるままに席を移った。そして、近くでストーブを良く見ると、驚きの声をあげてしまった。
「あっれ、これって、フジキの石炭ストーブだよね。良くまあ」
「冬はやっぱり、石炭じゃないとね。石油ストーブではとても」
女将は少し自慢そうに言った。
私は両手をストーブにかざしながら
「本当だね。暖かさが全然違うね」
と言った。
「そうでしょう。良かったわ、喜んでもらえて」
女将は、そう言いながらストーブの側に行くと、湯気をもくもくとあげている薬缶に、水を足した。
「飲み物は何にします」
女将はカウンターに戻りながら言った。
「えーと、少しウイスキーを飲んできたからね」
私はそう言いながら、カウンターの横に並べられたボトルを見た。
その中に、赤玉ポートワインがあった。昔、父親たちが、それを焼酎に割って飲んでいたのを思い出した。
「その赤玉ポートワインを、焼酎で割ったのをもらおうかなあ」
「あら、珍しいわね」
と女将は言うと、素早く壜を取り、グラスに注ぎ焼酎と一緒に混ぜ私の前に置いた。
私は、懐かしそうにグラスを手にすると、一口飲んでみた。美味しかった。
「こんな味がしたんだ。実はこれを飲むのは、今夜が初めてなんだ。その壜を見たなら、昔親父たちがたまあに、こうして飲んでいるのを思い出してね」
「そうね、男たちはこうして飲んでいたわね。でも、この赤玉だって、いつでも買えるわけじゃなかったからね」
女将も思い出すように言った。
「女将さんも、昔炭鉱にいたのかい」
「ええ、あっち、こっちとね」
女将はお通しの煮付けを、小鉢に盛りながら言った。
「俺も、昔大夕張っていう炭鉱街にいたんだよ」
「大夕張って、あの夕張の奥にあった街ね。どうりで入ってきたときから、炭鉱の臭いがしていたもの」
「炭鉱の臭いって、どんな臭いさ。俺臭いかな」
私はそう言いながら、服の臭いを嗅ぎ出した。
「ばかね。鼻で感じるような臭いじゃないのよね」
と女将は少し笑いながら言った。
そして
「人間ね、生まれ育った土地の臭いってね、一生消えないのよ。どんなに時がたっても、たとえ街がなくなって、原野になってもね。だって、その土地が、みんな記憶しているんだから」
と私のグラスを見ながら言った。
私は、女将の言うことが、分かるような気がした。たとえ原野になっても、その土地が記憶している。その通りかもしれない。
「そうだね。たとえ原野になっても、土地が記憶している。だから、その土地の臭いも一生消えない」
私は、一口飲みながら言った。
「そんなに感心しないでくださいよ。ただ、そう思っただけなんですから」
と女将は少し恥ずかしそうに言った。
「女将さんも何か飲むかい」
私は親しみを込めて言った。
「それじゃ、同じ物いただこうかしら」
女将はグラスを手に取ると、一緒に乾杯をした。
「今年も一年間、ご苦労様でした。色々と大変だったのでしょうね。今年だけではないわ、故郷を出てから、随分と頑張られたのでしょう。私ね、人を見ると、その人の今までの歩みみたいものがわかるの。一生懸命働いて、ここまで出世できたのだから、立派なものですよ。本当に、ご苦労様」
そう言うと、女将はもう一度私のグラスに乾杯をした。
「ありがとう」
私は少し照れ笑いを浮かべ、もう一度グラスを傾けた。ああ、美味しい酒だ。
私は、女将の言葉が嬉しかった。確かに自分なりに、精一杯今日まで生きてきた。だが、そのことを親兄弟からも、こんな形ではっきりと、誉められたことはなかった。それだけに、今夜は妙に嬉しかった。
その後、女将と炭鉱での生活の話や、私の家族の話などをしながら、小一時間ほど飲んでいた。そんなに飲んだつもりはなかったが、やはり焼酎割りは効いてきた。そのうち、女将とも、初対面でないような気がしてきた。今夜が初めてであったが、居心地の良い店であった。
やがて店を出るとき、奥の部屋を見るとギターが立てかけてあった。私は女将に礼を言って店を出ると、西線六条の電停に向かって歩き出した。
「ああ、店の名を聞くのを忘れたな」
と思い出したが、次に行ったときに聞けば良いとそのまま歩き続けた。
電停には、若い男女が立っていた。女の方は、少し男に寄り添っていた。二人は恋人なのだろうか。きっと、何処かで食事でもした帰りなのだろう。
そんなことを考えているうちに、電車がやって来た。
私は再び、すすきの行の電車に乗った。もう終電に近い時刻なのか、混み合っていた。
外の寒さから開放され、暖かい空気に包まれると、私は急に酔いを感じてきた。そして眠気もさしてきた。そのときの私は、傍から見ると、随分と酔っているように見えたのだろう。まだ、学生のように見える若い女性が、席を譲ってくれた。最初は恐縮しながらも、結局は座ってしまった。そしてほんの数分、私は眠ってしまった。
電車が動き出す振動で、目が覚めた。
周りを見ると、乗客は私と、先ほどの男女の三人だけになっていた。
私は、車窓から外を見た。電車は白い雪煙をあげながら走っていた。良く見ると、そこは原野であった。電車は、果てしなく広がる雪原を、ライトで照らし出し走っていた。
そこは、私が生まれ育った街に繋がる、湖沿いの道であった。
やがて、右手には炭住の灯りが見えてきた。まるで、暗闇に浮かびあがる生き物のように、爛々と輝いていた。
この灯りの下で、沢山の人たちが、生活をしていた。今は生活の痕跡もなく、一面の原野になってしまったが、この土地には、人々の営みが、確かに刻み込まれている。
やがて、駅前のバス停が見えてきた。そこには、札幌行きのバスが停まっていた。
バスには、一人の少年が乗っていた。沢山の同級生が、見送りに来ていた。少年は緊張しながらも、必死で笑顔を繕っていた。そこにいるのは、十八歳の私であった。見送りの中には、父と妹もいた。母は、見送るのは嫌だと言って家にいた。
これが、故郷との最後の別れであった。その後、私は再び帰ることはなかった。それから間もなく、炭鉱は閉山となり、人々は離散してしまった。
私は、車窓から故郷を見ながら
「あの頃の街を、もっと、しっかりと見ておけば良かったなあ」
と呟いた。
本当は、もっと、もっと、沢山故郷に帰りたかった。そんな思いが、胸に込みあげてきた。そして涙が流れ出した。走り去るバスも、見送る友人たちの顔も、涙で霞んでしまった。
私は、しばらくそのまま、故郷のバス停を見ていた。
突然、車窓は暗闇に包まれた。そして、徐々に明るくなり、桜の花びらが舞い出した。桜の木の隣に、古いアパートが見えてくる。そこは、かつて和子と暮らしていた、アパートであった。
和子は、小学校五年のときに、美唄から母親と一緒に、この街にやって来た。何故か父親はいなかった。だが、どうしていないのかは、ついに聞くことはなかった。
和子の母親は、街で小さな飲み屋をやっていた。
中学一年のときに、和子と席が隣になった。和子は、周りの女子生徒とは少し雰囲気が違っていた。男子からは、どこかミステリアスな和子が、気になる存在になっていた。
ある秋の日の放課後
「家に遊びに来ない」
と和子から誘われた。
私たちは人目を避け、途中で待ち合わせをし、和子の家へと行った。私は女の子の家というよりは、和子の家が飲み屋であるということに、興味があった。
店の入口から家の中に入った。母親が出てきて、私たちを迎い入れた。確か和服であったような気もするが、顔はもう覚えていない。
私たちは、店のカウンターの前の椅子に、並んで座った。
和子の母は、炭火を熾すと
「好きなもの何でも焼いてあげるから、言ってごらん」
と優しく言ってくれた。
「ねえ、山口君 焼鳥おいしいよ」
と和子も言った。
私は以前から、ホルモンに興味があった。クラスの男子の間で、ホルモン焼が話題になったことがあった。焼鳥なら何となく分かるが、ホルモン焼については、誰も確かなところが分からなかった。
「結局、ホルモンって何だべなあ」
そう言うと皆黙り込んでしまった。
「山口君、遠慮しないで言ってちょうだい」
再び和子の母が促してくれた。すると
「ホルモンお願いします」
と私は思い切って言った。
「えっ、山口君ホルモン好きなんだ。将来飲んべいになるね」
と和子の母は笑いながら言った。
「そういう訳ではないんだけど」
私は下を向いて、少しはにかみながら言った。そして、何気なく店の奥を見ると、ギターが立てかけてあった。そう言えば、店の様子もさっきの店と同じような気もする。あの女将も、どことなく雰囲気が、和子の母に似ているような気がしてきた。だが、それも遠い昔のことで、今となっては、はっきりとはわからない。
ただ和子に
「おまえ ギター弾くのか」
と聞いたところ
「あのギターお父さんのものなの。お母さんが、いつも大切そうにしているんだ」
とぽつりと言ったのを、今でも覚えている。
初雪の降る頃に、和子は父親と一緒に暮らすことになったと言って、青森の中学校へ転校して行った。それ以来、音信もなく和子のことは、すっかり忘れていた。
それから七年後の夏に、私たちは大通公園で偶然に出会った。
何度か会う内に、私たちは恋に落ちた。そして、私は和子のアパートに、転がり込んだ。
あの頃、私は昼間は小さな工場で働き、夜は大学の二部に通っていた。両親は、閉山後神奈川に職を求め、妹と三人で暮らしていた。私は一人札幌に残っていた。仕事と学校の往復、そして生活の雑事に追われ、私は疲れていた。
そんなときに、和子と再会した。和子は、私に安らぎを与えてくれた。だが、私は和子に何を、与えることができたのだろうか。
夏の暑い日は、アパートの窓を開けると、路面電車の音が聞こえていた。
あの頃は、アパートがあった円山公園まで、まだ電車が走っていた。
一度だけ和子に
「お母さん青森にいるのか」
と聞いたことがあった。
和子は、しばらく考えて
「お母さんのことは、もういいの。お父さんのことも」
と淋しそうに言った。
それから私は、和子にお母さんの話はしないようにしていた。
秋も深まった頃、和子は妊娠した。
「あのね、私、赤ちゃんができたみたい」
和子は、デパートの勤めから帰ってくると、少し小さな声で言った。
私は、黙って天井を見つめ、溜息をついた。そんな私を見ると和子は
「大丈夫、私おろすから。ねえ、だから心配しないで」
と私の顔を覗き込むようにして言った。
その夜、私はとうとう和子に、何も言葉をかけなかった。それでいて、自分のエゴ、狡さを、和子に突き刺すように、投げつけていた。
雪の降る前に、和子は一人で病院へ行き、子供をおろした。私は、そのことに気づかない振りをして、何もなかったかのように暮らしていた。和子も、いつもどおりに生活しているように見えた。
その年のクリスマスに、和子はいなくなった。私は泊まり明けの仕事を終え、一日遅れのプレゼントを抱え、アパートに帰った。部屋に入ると、石油ストーブだけを残し、和子は荷物ごと消えていた。台所には置手紙があった。
あの日以来、本当は、私は和子を恐れていた。そして、いつ別れが来るのかと、怯えていた。
私は、手紙を手に取ると、申し訳ない気持ちで一杯になってきた。そして、これ以上自分のエゴと向き合うのが、たまらなく辛くなってきた。結局、私は手紙を読む勇気もなく、破り捨ててしまった。そして、アパートから逃げ出した。
あれから、クリスマスになると和子のことを思い出し、あの手紙には何が書いてあったのかと、思い巡らすことが多くなってきた。
車窓からは再び、桜の花びらが舞うのが見えた。私には、花びらが、あの日破り捨てた手紙の、紙吹雪のように思えてきた。
「ああ、酷いことをしてしまった」
私はそう呟くと、目を閉じた。そして、心の中であの日の和子に、何度も詫びていた。ふと人の気配がすると、あの男女が私の前に立っていた。恐る恐る二人の顔を見ると、男は悲しそうな目で私を見つめ、女は涙を流していた。
私は思わず
「許してください」
と叫んでしまった。
そのとき、電車は急に停まり灯りが消えた。そして、再び灯りが点くと、二人は消えていた。
しばらくすると、電車のドアが開き
「お父さん、早く」
と小さな女の子が、私を見て手を振っていた。
私は驚いた。そこには、まだ幼稚園生ぐらいの長女がいた。そして、妻と次女も立っていた。
私は、あわてて電車を降りた。そこは、かつて親子四人が暮らしていた、中の島通のアパートの前であった。
「お父さん、みんなで、丸万に行くんだよ」
次女は、甲高い声でそう言うと、私に手を繋いできた。久し振りに感じる、幼子の手の感触であった。小さな手の温もりが、とても懐かしくて、胸が一杯になってきた。
丸万は、私たち家族が、馴染みにさせてもらっていた、寿司屋であった。
小さな港町から、中の島通に初めてきた頃、私たち夫婦は、三歳の幼児と赤子を抱えていた。そんな子連れで、遠慮しがちに丸万寿司に入った。幼子と一緒では、店に嫌がられるかと思い、少し気持ちが萎縮していた。
店の大将と女将さんは、そんな私たち親子を、優しく迎えてくれた。それどころか、帰りには、子供にお菓子まで持たせてくれた。
それから、私たち家族は、丸万寿司の馴染みになった。「お祝いごとは丸万で」が、家族の合言葉になっていた。下の子が幼稚園生になるまで、私たちは中の島通のアパートで暮らした。今から思えば、懐かしい子育ての時期であった。
私は、下の子と手を繋ぎながら、丸万へと歩き出した。
やがて、暖簾が見えてくると、子供たちは駆け出した。上の子が先に店の戸を開けると
「お姉ちゃんずるい」
と下の子も後から続いた。
「いらっしゃいませ」
と大将の穏やかな声が、聞こえてくる。
「あらっ、よく来たわね」
後から女将さんの嬉しそうな声も、聞こえてくる。
私たちが店に入ると
「外は寒かったでしょう」
と大将は、ストーブの側の椅子に座るように、促してくれた。
女将さんも
「いらっしゃいませ」
と弾むような声で迎えてくれる。
こうして私たち家族が、丸万寿司で過した大切なときは、長く続くことはなかった。私たちが中の島通から転居した後、大将は店を閉めてしまった。だが、今夜はこうして、また丸万寿司で皆が揃うことができた。
大将も女将さんも、あの頃のままであった。ずっと、ずっと会いたいと願っていた、大切な人たちであった。
丸万のカウンターは、相変わらず良く磨き込まれていた。店の入口のところには、女将さんが丹精に生けた花が、置かれていた。本当に気持ちの良い店だ。
「今夜は、お嬢さんたちも揃っているから、記念に写真を撮らせてもらいますよ」
と大将が言うと、女将さんは、奥から大将の愛機を持ってきた。
「カメラって言ったって、いつもの使い捨てカメラですがね」
と大将は笑いながら言って、私たちにレンズを向けると、シャッターを切った。
「念のために、もう一枚写しますよ、いいですか」
大将は、名カメラマンのように、しっかりとまたシャッターを切った。
丸万の大将は、写真が好きであった。何かにつけ、大将の愛機でお客さんを写していた。
あの頃の家族写真は、どんなアルバムに収められているのだろうか。少し年老いた大将と女将さんは、それらの写真を見ながら、どんな話をしているのであろうか。きっと、沢山の思い出話で、幸せなときを過しているに違いない。
「お嬢さんたちは、何を握りますか」
大将は娘たちに尋ねた。
二人とも大将が「お嬢さん」と話しかけるのが、少し大人扱いされたようで、とても気に入っていた。
「私は鉄火巻を願いします」
と上の子が言うと
「私はまぐろを巻いてください」
と下の子が言う。
妻は「それを鉄火巻と言うのよ」と嗜めると、下の子は
「マグロでもいいんだよね。ねえ、おじさん」
と大将に話しかける。
大将は「さあ、どうでしょうね」と優しく答えると
「長さはどうします」とまた娘たちに尋ねた。
「私は一本のままでお願いします」
上の子はすぐに答えた。
「私は、半分でお願いします」
と下の子も答える。
腕の良い寿司職人に、巻物の長さを、自分好みにしてもらう。こんなことは、この子たちが大人になっても叶うものではないと、私も妻も思っていた。
私たち夫婦は、転勤で、色んな土地を旅してきた。そして、新しい土地に行くと、好みの寿司屋を探した。酢が効いていて、シャリの握りがしっかりしていること、この二つが条件であった。
丸万の寿司は、二人の好みにぴったりであった。それどころか、これ以上の寿司に出会うことはなかった。
子供たちの寿司が出来上がった後、私たちは、上寿司と刺身の盛り合わせを頼み、飲み始めた。
私はイカの握りを食べた。
「ああ、この味だなあ。大将、本当に美味しいです。丸万は、やっぱり最高だ」
私は顔一杯に笑みを浮かべ、嬉しそうに言った。
「本当にそうですね。だって、どこに行ったって、これ以上の寿司には、出会えなかったものね」
と妻も目を輝かせながら言った。
「そう言ってもらえると、嬉しいですね」
大将は女将さんの方を見ながら、少し照れ臭そうに言った。
「本当にありがとうございます」
と女将さんも嬉しそうに言った。
「おばさん、紙と鉛筆、貸してください」
食べ終わると、上の子が言った。そして、下の子と一緒に、小上がりの和室のテーブルの前に座った。
女将さんは、子供連れのお客さんが来ても良いように、子供が喜ぶような、折り紙、色鉛筆などを用意していた。
「はい、どうぞ」
と女将さんは目を細めて、娘たちに紙と色鉛筆を渡した。
子供たちは嬉しそうに
「ありがとうございます」
と声を弾ませて言うと、早速遊び始めた。
子供たちにとっても、丸万は寿司を食べるだけではなく、ワクワクする遊びの空間でもあった。
女将さんも、子供たちの横に座り、楽しそうに、子供たちの描く絵を眺めていた。
その間、私たちは大将と話をしながら、ゆっくりと飲んでいた。
今夜、ここには、全てが揃っていた。大好きな大将も女将さんも側にいる。何もかもが、幸せで満たされていた。
少し疲れた年の瀬に、暖かくて、懐かしくて、そして優しいものが、体の中に流れ込んでくるのを感じていた。
「大将、女将さん、いつもありがとうございます。今夜は何だか、とっても嬉しくて」
私は思わずそう言った。妻も横で頷いていた。
「ありがとうなんて、とんでもないですよ。私たちこそ、こうしていつも、娘さんたちと一緒に店に来ていただいて」
大将は、相変わらず控えめに言った。
女将さんも
「そうですよ」
と子供たちの顔を見ながら言った。
子供たちは、いつまでも女将さんの側で、絵を描き楽しそうに遊んでいた。
ああ、この時間が、いつまでも続けば良いのにと思いながら、私は大将と女将さんの顔を見ていた。そして、私は幸せに包まれ、いつの間にか眠ってしまった。
路面電車が電停に停まるときの振動で、私は目が覚めた。電車は終点「すすきの」に着いていた。
私は、ゆっくりと、電車の中を見渡した。そして、何故自分がここにいるのか、良く飲込めず、しばらく呆然として座っていた。街のイルミネーションも消えていた。時計を見ると、十一時をとうに過ぎていた。
そのとき、運転手がやって来て
「お客さん、終点ですよ。これで終電ですが、大丈夫ですか」
と心配そうに私の顔を覗き込むように言った。
私は、はっとして
「大丈夫です。大丈夫ですから」
と言うと、あわてて立ち上がり電車を降りた。すると、電停には妻が立っていた。
私は驚き
「どうした」
と聞くと
「だって、タクシーを拾おうかと思ってここまで来たら、電車にあなたとよく似た人が見えたもんだから、でも自信がなくて。こっちこそびっくりよ」
妻は、私を不思議そうに見ながら言った。
私は今夜のことを、どう説明したら良いのか分からず、曖昧な顔で黙っていた。
すると
「また飲み過ぎて、電車を乗り過ごしたのでしょう」
と少し呆れたように言った。
「どうも、そうらしいんだ。でも夢の中で、皆で丸万へ行って、大将と女将さんに会えたんだ」
私は少し声を弾ませて言った。
「あら、それは良かったじゃない」
妻も嬉しそうに言った。
今夜出会った人たちが、夢の中の出来事なのか、あるいは現実なのか、今の私には良くわからない。ただ、ひどく心が痛むこともあったが、全てが、私の今までの人生の足跡であったことは、事実であった。できれば、誰も傷つけずに生きてきたかった。だが、それ自体が夢なのかもしれない。
私は、今夜終電の電停で妻と会えたことに、どこか安堵していた。今夜のことは、後でゆっくりと妻に話そうと思った。妻なら分かってくれる、そんな気がしていた。
私たちは、タクシーを拾うと、マンションへと向かった。西線六条の電停に差し掛かったとき、私は咄嗟に
「運転手さん、そこ右に曲がってもらえますか」
と言った。
「あら、どうしたの」
と妻は不思議そうに言った。
「ちょっと、確かめておきたい場所があってね」
と私は曖昧に答えた。
電車通から角を曲がったところで、私はタクシーを降りた。妻も一緒に降り、私の後に続いた。私は、建物の前で立ち止まった。
確かに、そこに建物はあった。だが、もう何年も前から空き家になっている状態であった。屋根には雪が高く積もり、窓ガラスも破れていた。
「あなた、ここなの。随分と古い家ね」
妻は怪訝そうに言った。
そのときふと隣を見ると、雪の積もった空き地に「売地」と書かれた看板が、立てられていた。
「隣の空き地だよ」
私は咄嗟に、看板を指し妻に言った。
「この売地なの」
と妻は言った。
「うん、良い土地があるって、職場の人に聞いたものだから。ここを買って、家でも建てようかと思ってなあ」と私は言った。
「今さら、一軒家なんて。それに雪掻きは、もうこりごりですよ。そう思って、今のマンション買ったのだから」
妻は笑いながら、あっさりと言った。
「それもそうだなあ。今さら、雪掻きはなあ」
と私も言うと、タクシーに戻った。
今夜のことは、全て、路面電車の仕業なのだろうか。それとも、ただの幻なのだろうか。だが、路面電車に乗ることによって、私は懐かしい人たちと、会うことができた。そして、心が癒された。今年の年の瀬も、穏やかに過ぎようとしている。
私は、そんなことを思いながら、妻の手を、ぎゅっと握った。すると、妻も少し笑みを浮かべ、握り返してくれた。
眠りについた電車通を、タクシーは我が家へと走る。
(2011年 「さっぽろ市民文芸NO.28』 奨励賞受賞作)
(作者紹介)
夕張市鹿島生まれ
生まれてから高校卒業までの18年間を大夕張で過ごす。『ふるさと大夕張』にはしばしば投稿していたようだが、素顔は謎である。札幌在住。










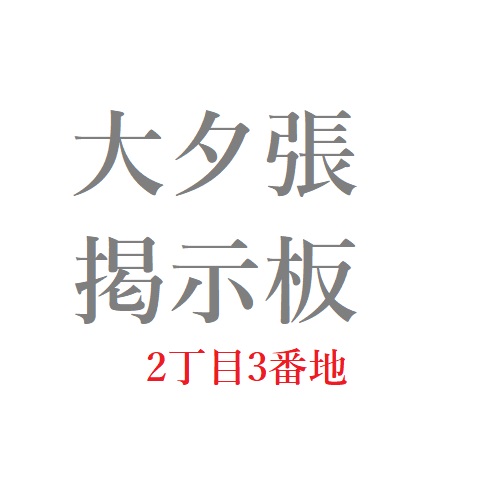









発表年順に、夕輝文敏さんの作品を紹介してきましたが、嬉しいお知らせです。
2011年、『さっぽろ市民文芸No.28』に掲載された奨励賞受賞作『路面電車に揺られて』を、今回、夕輝さんから、送っていただきました。
『ふるさと大夕張』には、初掲載になります。
夕輝文敏さんありがとうございました。
_
10年前の『新作』を、どうぞお楽しみください。