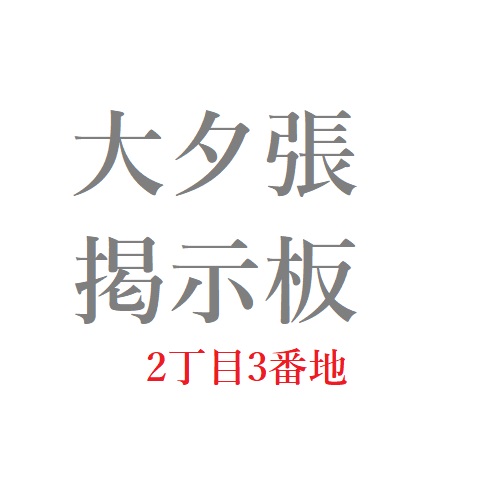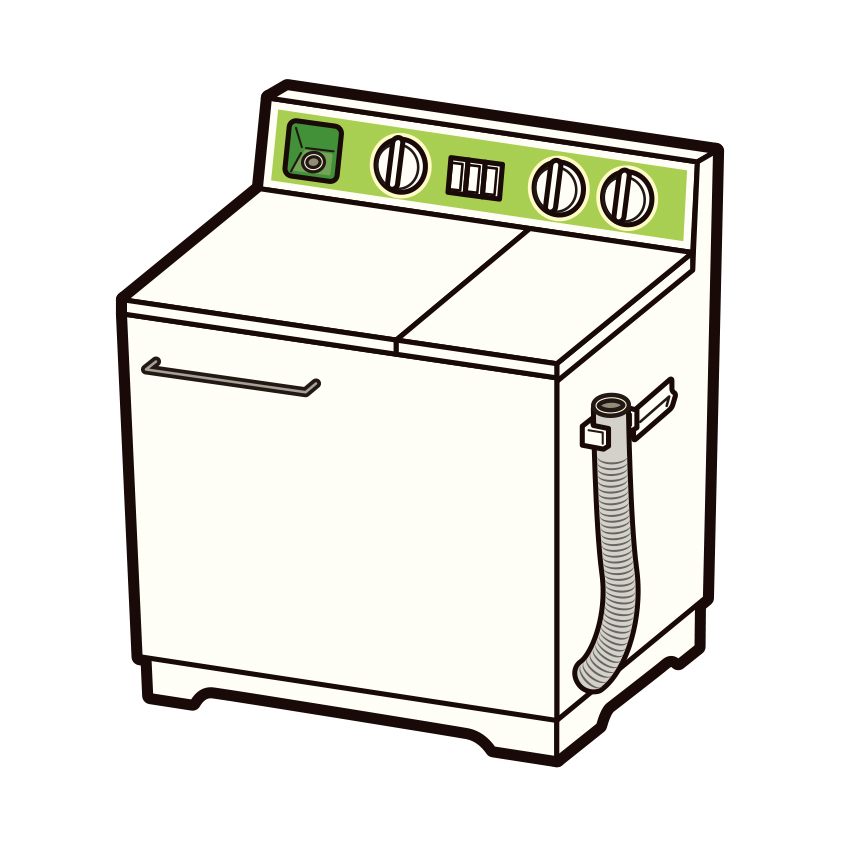迎え人(びと)|夕輝文敏

五月晴れのある日、洗車をしていると、女の子が近づいてきて、
「お父さん、ドライブに連れて行って」
と少し大きな声でいった。
周りを見渡すと洗車場には私しかいなかった。
女の子は私の前で立ち止まると、にっこりと笑った。
しばらく私はその子を凝視した。
間違いない。
そこには、まだ10歳ぐらいの長女がいた。
あの頃と同じく髪を肩まで伸ばし、Gパンにお気に入りの水色のトレーナーを着ていた。
長女を最期に見たのは、もうずっと以前のことであった。
鮮やかな色の花に埋もれて、静かに眠っているかのようであった。
あともうひと月で、24歳の誕生日を迎える頃であった。
「やっと姿を見せてくれたんだ」
私は心の中でそうつぶやいた。
「よしわかった。 何処へ行こうか」
と長女に尋ねた。
「あの小学校の校庭がいいな。大きな木があって、そこで焚火して、バーベキューもしたいなあ」
長女は目を輝かせていった。
私は洗車を済ませると、長女を乗せ、あの街に向かって車を走らせた。
あの街へは、もう10年以上帰っていない。
20年ぐらい前、チャット仲間たちと春と秋の連休には、あの街の小学校に集まっていた。
校庭のイタヤカエデの木のそばで、バーベキューをしたりして楽しんでいた。
子供たちも親についてきて、焚火をしたり走り回って遊んでいた。
いつしか集まりは消えたが、焚火と焼肉の記憶は子供たちの中に、楽しい思い出として植えこまれているようだ。
時折長女は、私の顔を見ると、ニコリと笑い
「楽しいね、お父さん」
といった。
私も
「そうだね、昔4人で色んな所へ行ったね」
と言葉を返した。
「お母さんたちも、来ればよかったのにね」
と長女は、妻と次女がいないことを、残念がっていった。
長沼を過ぎると、夕張に入った。そして清水沢にさしかかった。
駅のあたりから、黒煙が青い空にたなびいていた。清水沢駅に、蒸気機関車が入っていたのだ。
「お父さん、ここからあれに乗って行こうよ」
と長女は少し高揚した声でいった。
「汽車に乗りたいのか」
「うん。だって一度も乗ったことなかったから...」
「そうか、乗ったことなかったか。それじゃ、汽車に乗って行こうか」
私がそういうと長女は嬉しそうに
「うん...」
と大きな声でこたえた。
駅構内には、大きな黒光りする蒸気機関車が、煙と一緒に蒸気を噴き出していた。客車も3両つながっている。
私が、小高い丘にある高校に通学していたときに、乗っていた汽車であった。
私たちが乗った車両には、他に乗客はいなかった。
長女と私は、窓側の座席に、向かい合って座った。
「懐かしいなあ、お父さん、この汽車に乗って高校に行ってたんだ」
と私がいうと
「えっ、お父さんたちって、贅沢だったんだね」
と長女がいった。
「贅沢...」
「だって、私たちは地下鉄と電車しか乗ったことないもの。だから、やっぱりお父さんたち贅沢だよ」
私は、汽車通学が贅沢だという長女の話が可笑しくて、笑い出した。そして「そうか、贅沢か」といった。すると、長女もつられて笑い出した。
やがて汽車が次の駅に着くと、大きな犬を連れた少年が、同じ車両に入って来た。
少年は私たちのそばに来ると、頭をペコリと下げて微笑んだ。
少年は紺色のパンツに白いシャツを着ていた。
「あっ...」
と私は声を出した。
あの頃、校庭で長女たちと一緒に遊んでいた少年であった。
その少年はいつも大きな犬をつれていた。
長女は少年に
「ここに一緒に座ろう」
といい、窓側の席をあけた。
少年はうなずくと、犬を連れて私たちの前に座った。
長女は直ぐに犬をそばに引き寄せ
「よし、よし、いい子だね」
と頭をなぜた。
犬も尻尾を振って嬉しそうにしていた。犬も長女を覚えているようであった。
長女は動物が好きであった。しかし犬はとうとう飼うことはできなかった。
私は少年に
「この子の名前は」
と尋ねると
「バウだよ、お父さん、もう忘れたの」
と長女は少したしなめるようにいった。
「ああ、そうだ、バウだ、バウ」
と私も犬の頭をなぜた。
「バウ、みんな覚えていてくれて良かったね」
と少年も嬉しそうにいった。
バウは白い毛の長い大きな犬であった。人なっつこくて子供たちの人気者であった。
バウは私たちのもとを離れると、車両の中を嬉しそうに走り回り、時々私たちの顔を見ては少し吠えたりしていた。
やがて汽車はあの街の駅に着いた。
駅といっても駅舎はすでになく、閑散としていた。
私たちが降りると、汽車は直ぐに、もと来た方向へと戻って行った。
私たちが手を振ると汽笛を鳴らし、運転士さんがこちらを向いて手を振ってくれた。
あの頃の見慣れた顔であった。
「お父さん、行こう」
長女に促され私たちは小学校の手前の坂を登った。
校舎の建っていたあたりには、桜が咲いていた。
この街の桜は5月の後半前後に開花を迎える。
「今年もちゃんと咲いているんだ」
少年が嬉しそうにいった。バウもわかるのか、桜の木の周りを吠えながら回っていた。
校庭には一面タンポポの花が咲いていた。それは黄色に包まれた絨毯のようであった。
子供の頃は「タンポポの海」と呼んでいたのを私は思い出した。
校庭の奥にあるイタヤカエデの木の方を見ると、車が1台あった。
「あっ、おじさん先に来ていたんだ」
そういうと長女は駆け出した。少年とバウも続いた。
仲間内からは「焼肉奉行」と呼ばれている友人である。みんな省略して奉行と呼んでいた。
奉行は私の高校の先輩である。面倒見がよく、何をやらせても手際のよい人であった。
奉行は、炭の袋を取り出し、バーベキューの準備に取り掛かっていた。
私は
「来ていたんですか」
と声をかけた。
「今日はバーベキューしたいって聞いていたから、俺の出番だと思って。それに懐かしい顔も見たくてね」
奉行は、子供たちの顔を見ながら、嬉しそうにいった。
「そうだ、バウ、おまえの分もちゃんと用意したから待ってな」
奉行がそういうと、バウは一声吠えて、奉行の顔をなめようとした。
「バウ、おまえの気持ちはわかったから、落ち着け」
となだめていた。
かつて、春と秋には仲間たちとここに集まり、火をおこし、ふるさとを堪能していた。
子供たちが小さい頃は、我が家の大切な年間行事になっていた。
それも、子供たちの部活がはじまると、参加する機会もなくなり、集まりもいつしか途絶えてしまった。
でも、今日はこうしてまた集まることができた。
みんないい顔をしている。
イタヤカエデの木も風にそよいでいる。
のどかな時間が流れていく。
「お父さん、焚火やろう」
長女はバウの頭をなぜながらいった。
「それじゃみんなで小枝を集めてこよう」
少年も一緒に校庭横の草むらに入った。今頃の季節は雑草もなく地形がよくわかる。
見る人もいないのに、かつて家々の庭に植えられていた春の花たちは、競うように咲いていた。
バウは動こうとせず、奉行のそばに張り付いていた。
小枝も集まり火がおこされた。町の中では焚火はできないので、あの頃、ここに集まる子供たちにとっては、とても神聖な儀式であった。
焚火の中にアルミにくるんだ芋を入れることもあったが、焼き加減が難しく、黒焦げになることが多かった。
炎の中に皆の顔が浮かび上がってくる。
時折ラインで近況を連絡しあっているが、それぞれ元気でいるようだ。
我が家には、カメラ好きの奉行が撮った写真があった。
奉行自慢のフイルムカメラニコンF2で撮ったものである。
もう十数年前の秋に集まったときの写真だ。大人も子供もみんないい顔をしている。傍らにはバウもいる。
あの中で、少年と少女だけが思い出の人となってしまった。二人ともまだ20代前半で、それぞれ病気と事故で早逝してしまった。
「さあ、準備できたぞ」
みんなを呼ぶ奉行の声が校庭に響いた。
「おじさんの塩ホルモン本当に美味しいね」
長女は少し熱い肉を口の中で持て余すように、それでいて嬉しそうにいった。
「懐かしい味だなあ。このホルモンお父さん大好きだった」
少年も過ぎ去ったあの日々を思い出すようにいった。
「おじさんはみんなに喜んでもらえるのが、一番うれしいんだ。さあ、どんどん食べな」
奉行は嬉しそうに肉を焼きだす。
振り返ってみれば奉行がいたからこそ、あの春、秋のバーベキューは続いたのだと思う。今度会ったなら、改めて礼をいおうと思った。
それからみんなで食べながら、とりとめのない話をしばらくしていた。
「ああ、食べた。おじさんもうごちそうさまだよ。ありがとうございます」
少年は箸を置くと満足そうにいった。
「私ももうお腹がいっぱい。おじさん、どうもありがとう」
と長女もいった。
「えっ、まだ肉こんなにあるのに」
奉行は不満そうにいうと
「そうだ、腹ごなしにみんなで神社山に登ろう。久し振りだろう。うんそれがいい」
と納得したようにいった。
「そうだな。神社の桜、今年も咲いているのかな」
私はそういうと、ホームページにのっていた写真を思い出した。
大人たちが社殿の横に輪を作って座り、楽しそうに花見をしている写真である。その正面のやや右に桜の木が入っていた。
かつて人々が楽しんだ空間が、のどかに息づいていた。私の好きな写真である。
神社山に続く道を登るにつれ、かつて炭住が張り付いていた地形が見えてくる。この大地にかつて2万もの人々が生活していた。
この原野だけの風景では、外から入って来た人は想像することもできないことだろう。
やがて階段に差しかかった。
まだ雑草の伸びていないコンクリートの階段がはっきりと見える。
バウは先に走り出し階段をどんどん登っていく。そして「早く」とせかすように私たちに吠えた。
バウに続いてその階段をみんなで登りきると、たくさんの黄色い旗が見えてきた。
その中に「鹿島中学校卒業生」と書かれた大きな旗があった。かなり痛んでいたがその文字はまだ読み取ることができた。
少年は大きな木に括りつけられたその旗を手に取ると
「これ、お父さんたちの旗だ。ここにお父さんと一緒に来たことがあるんだ」
と嬉しそうにいった。
バウは少年の気持ちがわかるらしく、嬉しそうに尾っぽを振りながら木の周りをぐるぐる回っていた。
「お父さん、ここみんなと来たことある。旗もまだあって良かったね」
長女も嬉しそうにいって、私の手をぎゅっと握ってきた。
小さな手だ。それもとても暖かい愛しい手だ。この手と一緒につくってきた思い出が沢山ある。
長女のぬくもりを感じながら、胸にこみあげてくるものがあった。
すると、少年も私のもう片方の手をぎゅっと握り、そして微笑んだ。
多分これは現実の世界の出来事ではないのだろう。
かといって、すぐに消えてしまう幻のようなものでもない。
年齢を重ねるにつれ、愛しい人たちを多く見送ってきた。
でも愛しい者たちは消え去ったのではなかった。むしろ以前より身近に感じることが多くなってきた。
送った人たちはもう現実の世界にはいないのかもしれない。
でも、この世界で日常の中にいる私たちは、たくさんの思い出を持っている。
思い出の中では、私たちは愛しい者たちをいつでも迎い入れることができる。
日常の私たちの世界と、思い出の中にいる愛おしい者たちとの世界とは、実は境目がないのではないか。むしろ現実の世界そのものが、沢山の思い出に包まれているのかもしれない。
私は少年と長女の手のぬくもりを感じながら、そう強く思った。
「久ぶりにここで写真撮るぞ」
奉行はそういうと、自慢のニコンF2を三脚に固定した。
「あっ、少し逆光だからストロボもつけるか」
奉行はストロボをバックから取り出した。
皆がならぶと
「おじさん、バウも一緒に撮ってね」
と長女がいった。
「そうだね。いつもおまえも一緒だったかならあ」
少年はバウをそばに引き寄せた。
「ようし、セットできた。さあタイマーにあわせて映るぞ」
奉行がそういうと間もなくストロボが光った。
強くそれでいて優しい光が、ふるさとと皆を包み込んだ。
「ちょっと、起きてよ。もう終わったから帰るわよ」
妻の声で私は目をさました。
今日は長女の命日であった。妻と二人で寺の納骨堂にお参りに来ていた。
読経の後、妻は管理費の支払いで事務所に行っていた。私はロビーでほんの数分間まどろんでいたようだ。
寺の大きな駐車場の向こうでは、最近できた洗車場が忙しく働いていた。
そこにいる親子に、私の目が留まった。
父親の横には、10歳ぐらいの水色のトレーナーを着た女の子が、布を持ちふき取りを手伝っていた。
女の子は、何気なくこちらを振り向くと、ニコリと笑った。
「可愛い女の子ね」妻が目を細めていった。
「そうだな」
私はそういいながら、少女の微笑みの中に長女の姿を見ていた。
愛しい者たちは消えたりしない。
私たちが思い出の扉を開き、迎い入れると、いつでも私たちのそばにいる。
(2021年5月17日 発表)
(作者紹介)
夕張市鹿島生まれ
生まれてから高校卒業までの18年間を大夕張で過ごす。『ふるさと大夕張』にはしばしば投稿していたようだが、素顔は謎である。札幌在住。