イリュージョン /大晦日の奇跡|夕輝文敏

(目次)
- 路地裏
- 目覚め
- サイレンの音
- 父の背中
- 年越しの夜
- 葉 書
路地裏
隆一はその夜いつになく酔っていた。
同僚と別れた後、すぐにタクシーを拾おうとしたが、どれも満車であった。年の瀬のススキノは、人で混み合っていた。
隆一は仕方がなく、冷たい風に当たりながら、酔いを覚まそうと歩き出した。
しばらく歩くと、行きつけの寿司屋にでも寄ろうと思い、ふらつきながら路地裏に入った。
途中まで行くと、いつもの道が行き止まりになっていた。
「あれ、道をまちがえたかな」
隆一は後ろを振り返ると、いつもの見慣れたビルのネオンが目に入ってきた。
「やっぱり、この通りでいいんだよなあ」
そのとき、ふと左側を見ると、人一人がやっと通り抜けられるような、隙間がビルの間にあった。
隆一は、その隙間に入って行った。
入ってみると思ったより奥行が深く、進むにつれ暗闇が迫ってきた。
どのくらい歩いたのだろうか。街の喧騒も消えた頃、やっと明かりが見えてきた。
「こんなところに、店があったかなあ」
さらに進むと、裸電球の街路灯に照らし出された通りが見えてきた。
「あれ、この通りは・・・」
隆一は酔った目で、凝視した。それは、隆一が生まれ育った街の駅前通りにそっくりであった。通りは人の気配もなく、深い雪に包まれ静まり返っていた。
明かりの消えた建物を、街路灯がやさしく照らし出している。
隆一は、ゆっくりと踏み入った。
静けさの中で、雪を踏みしめる音が響く。
郵便局があってその向かいには詰所がある。そして、その向こうには生協も見える。
「まさか、こんなことが・・・」
冷静に考えようとしても、酔いが回っていて、これが現実なのか夢なのかも判断ができない。隆一はとにかく先に進んでみることにした。
一軒だけ明かりのついている建物があった。近づいて見ると、BAR・エルボンと書いてあった。その隣には食堂があった。
「これは、あの街そのものじゃないか」
隆一は混乱して叫んでしまった。
そのとき、BAR・エルボンのドアが開き、若い女が出てきた。それは、子供の頃見覚えのある顔であった。
「ちょっと、いつまでそこに立ってぶつぶつ言っているのさ。さあ、中に入って」
隆一は女の後について、店の中に入った。
カウンター式のボックスバーで店の中には誰もいなかった。
隆一が立ったまま店の中を見渡していると
「さあ、ここに座って」
と、女はイスを指した。
「この店には、子供の頃おやじを迎えに来たことがあったなあ」
隆一は座りながら言った。
「そうだね。男たちがいつまでも飲んでいると、母親に言いつけられて、子供たちが良く来たものさ」
女はそう言うと、レコードプレイヤーにドーナツ版のレコードをのせた。
スピーカーからは、水原弘の「君こそわが命」が流れてきた。
「今夜は少し飲み過ぎたようだ。こんなことがあるはずがない」
「そうよ、これはただの幻よ。ここには、あんたみたく心にぽっかりと穴があいている子供たちがやってくる。そして、それを埋めたくて幻と出会う・・・」
女はそう言うと、タバコに火をつけた。
「子供たちって・・・俺はもう40を過ぎたおやじだよ」
隆一は少しムキになって言った。
「いくら大人たって、この通りに入ったときから、もう一度あの頃に帰りたいと思っているくせに。だからもう子供の心に戻っている。あんたさえその気なら、もう一度あの頃に戻してあげてもいいんだよ」
女は意味ありげに笑いながら言った。
「そんなこと、できる訳ないだろう。だいたいあんた変だよ・・・」
女は子供をあやすような目で隆一を見て、目の前にボトルとグラスを置いた。
「それができるのよ。この酒をグラスで一杯飲み干すとね。でも、この酒は高いわよ。そう、今夜は、一杯三万円でいいわ。さあ、どうする」
隆一は、心の中を見透かされているような気がしてきた。どうせ手元に残らない金なら、これが嘘ならそれはそれでもいいと思った。そして、もし本当なら・・・。
「じゃ、一杯もらおう」
隆一は、財布から三万円を出すと、カウンターの上に置いた。
「あんたは運の良い人だわ。ここでことわれば、心の隙間は一生埋まることなく死んで行くところだったのに。こんな夢なんて、この街を出て行った子供たちが、みんなかなうものではないわ。でも、この夢はその日の夜中までよ。再び朝を迎えることはできないの。はい領収書。これが、あんたの夢の証人になるわ」
隆一は領収書を受け取ると、財布の中に入れた。女はグラスに琥珀色の酒を注いだ。
「さあ、みんなに会っておいで・・・」
隆一は女の顔をじっと見た後、一気にグラスを飲み干した。すると、頭が割れるように痛み出し、意識を失ってしまった。
目覚め
隆一は、激しい喉の渇きを覚え、目を覚ました。
布団から起き上がろうとしたとき、いつもと家の様子が違うことに気がついた。
「まさか、こんなことが・・・」
隣の布団を見ると、妹の道子が寝ていた。それも小学生のような顔をした妹であった。
豆電球の明りの下、目を凝らして見ると、居間には父と母が寝ていた。
隆一は、混乱しながらも、水を飲もうと布団から抜け出し、立ち上がった。すると、背丈が小さくなっていることに気がついた。そっと流しまで行って、電球をつけると鏡を覗いた。そこに写っているのは、小学生の自分の顔であった。
「えっ・・・」
隆一は、驚きの声を上げてしまった。
そのとき、隆一の母は、まぶしそうにこちらを見ながら
「隆一どうしたの、こんなに朝早く。風邪引くからまだ布団の中に入っていなさい」
と言った。
「うん、ちょっと喉か渇いたもんだから。すぐ寝るから」
隆一は、自分の異変に気づかれないように言った。
布団に入るともう一度隆一は、エルボンでのやりとりを思い出してみた。確かに、あの女の言ったとおりになっていた。
(あの女の言ったことは本当だったんだ)
あれこれ考えているうちに、隆一はこうなったら、今の現状を受け入れるしかないと、踏ん切りをつけることができた。すると心が落ち着き、再び深い眠りへと落ちていった。
「お兄ちゃん、起きて。もう少しでご飯だよ」
道子は、隆一の体を揺すりながら言った。
隆一は目を開けると
「ああ、わかったよ」
と言った。
「明け方に電気なんかつけて、もぞもぞしていたから、二度寝してまだ眠いんだべさ。でも、今日は年越しで忙しいんだから、もう起きてよ」
そこには、若き日の母が朝げの支度をしていた。真赤に燃えている石炭ストーブの傍らでは、父が新聞を読んでいた。
「今日は大晦日か。年が明けたら隆一も中学生だ。あの洟垂れ坊主が、中学生だもんなあ。早いもんだ・・・」
隆一を見ながら父は言った。
(今の俺は、小学校六年生なんだ。もうじき中学に入るんだ。でも、待てよ。父さんが落盤事故で亡くなったのは、確か中学生になって間もなくだったな。じゃ、今日は親子4人で過ごした最後の大晦日だ・・・)
隆一は、偶然手に入れた今日一日を、悔いのないように過ごそうと決めた。
朝ご飯が済むと父は、
「さあ、父さんは二番方で帰ってきたから、もうひと眠りするか」
と言って、流しの下の台から一升瓶を取り出した。
隆一は父のところへ行き、
「父さん、今年もご苦労様でした。酒注いであげるよ」
と言った。
「ほう、さすが中学生になるだけあって、感心だなあ。したら、一杯ついでもらうべ」
隆一は、父が差し出したグラスに酒を注いだ。
父は隆一の顔を見て微笑むと、上手そうに飲んで、布団の中へと入っていった。
「隆一、父さん疲れているから、道子連れて昼までスキーに行っておいで」
と母が言った。
三交代で働いているのに、父には仮眠を取る専用の部屋もなかった。六畳二間の長屋で、親子四人が生活をしていた。
「母さん、兄ちゃんと一緒じゃいやだ。だって、いつも置いてきぼりするんだもの」
と道子が母に言った。
「道子、今日はちゃんと一緒に滑るから。だから、父さん寝かせてやろう」
隆一は道子の側に行き、諭すように言った。
サイレンの音
二人がスキー場に着くと、すでに沢山の子供たちが滑っていた。
神社側の斜面では、赤いセーターを着たスキー部の上級生たちが滑っていた。今夜の松明滑走にむけて練習をしているようであった。
隆一は、ここに来る途中、道子と話をしながら、子供の頃良くこうして一緒に遊びに来ていたことを思い出していた。
今は、隆一の方からはほとんど連絡をしなくなったが、子供の頃は、道子が一番身近な存在であった。
隆一は、道子がとてもいとおしい存在に思えた。そんな隆一の気持が伝わるのか、道子もうれしそうに隆一の側にいた。
しばらくすると、隆一の友達もやってきたが、誘いを断り、道子と一緒に滑っていた。道子はまだ力が弱く、ロープ塔は苦手であったので、隆一が後ろから支えてやった。
「いつもの兄ちゃんでないみたい」
そんな隆一に道子は遠慮しがちに言った。
「そうだな、いつも道子のこと置いてきぼりしてたからな。でもな、道子のことが嫌いだからじゃないんだ。俺ぐらいの小学生って、妹を連れて歩くのが照れくさいんだよ。でも、いつだって、道子が妹で良かったって本当は思っているんだ。だから、ごめんな・・・」
隆一は本心からそう思って言った。
「うん、わかっている。道子も兄ちゃんのこと大好きだから」
小学校3年生のオカッパ頭の道子は、少し照れながら下を向いて言った。
やがて、昼近くになった頃
「道子、兄ちゃん、学校に寄ってから帰るから、一人で先に帰ってくれるかい」
「うん、わかった。母さんにも言っておくから」
「じゃ、車に気をつけてな」
隆一がそう言うと、道子は不思議そうな顔をして、
「兄ちゃん、車って自動車のこと。そんなのめったにないよ」
と言った。
「あ、そうだな、間違えた。でも、家まで転ばないで、ちゃんと滑って帰るんだぞ」
道子と別れた後、スキー場から真っ直ぐな一本道を滑って行くと、やがて大きな校舎が見えてきた。
隆一は校舎の前に着くと板をはずし、玄関の大きなガラスの扉を押した。静まりかえった校舎は、冷え切った空気に包まれていた。正面には体育の授業で使うスキーが立て掛けられていた。
当直室を覗いたら、昼時のため家に帰ったのか、当直の先生もいなかった。
隆一は階段を上り、三階の松組の教室へと向かった。
三階にたどり着くと、廊下の窓から街を見渡した。沢山の住宅が大地に張り付いていた。人の往来も見える。隆一は目を閉じ、後年原野になった街の姿を思い浮かべた。
そして、再び目を開け街を見た。
「ああ、昔のままだ。この街には、これが一番似合う」
隆一は、活気に満ちている街を見ているうちにうれしくなり、心までが弾んでくるのを感じた。
教室の戸を開けると、そこにはあの頃のままの空間があった。木の机を手でなぞると、ひんやりとした感触が懐かしさを体中に伝えてきた。
そのとき静寂を破り、昼時を告げるサイレンが鳴り響いた。
隆一は一瞬体が硬直した。あの日も、坑内事故を告げるサイレンが、繰り返し鳴り響いていた。
その日、父は二番方で坑内に入っていた。
母は詰所から知らせが来ると、直ぐに隆一と道子を連れ、進発所へと駆けつけた。
その夜遅く父は運び出されたが、既に息絶えていた。落盤事故で隆一の父は、再び陽の光を見ることなく三八才の生涯を閉じた。
隆一は、急に父に会いたくなり、急いで階段を駆け下りると、スキーを履いて家へと向かった。
父の背中
隆一は、息を切らせ家の前までスキーを滑らせてきた。
「ただいま」
勢い良く玄関を開けると、居間では母が石炭ストーブの上で、餅を焼いていた。そしてテーブルには、父と道子が座っていた。
「隆一、腹減ったべ。早くこっちに来て餅食え」
と父が言った。
隆一はうれしそうに頷くと、父の横に座った。砂糖醤油をつけ餅をほおばると口の中に甘い味が広がった。どんぶりには、少し凍りついたニシン漬が盛られていた。シバレタ漬物を食べるなんて、この街を出て以来であった。どんな豪華なご馳走よりも、美味しい昼食だと隆一は思った。
こんなにも心が満たされる食卓が、木造長屋の小さな空間にあったことを、隆一は長いこと忘れていた。そして、かつて家族という形の身近な幸せがあったことを思い出していた。
やがて、父は煙突掃除をすると言って立ち上がった。
「父さん、俺も手伝う」
隆一がそう言うと
「そうか。隆一にしては珍しいなあ」
と、父は隆一の頭をなぜ、一緒に外へ出た。
父と一緒に屋根に登ってみると、長屋のあちらこちらで、同じように煙突掃除をしているのが見えた。
真っ白に積もった雪が、見る見る煤で黒くなっていく。
煙突掃除が終わると、隆一は父と一緒に共同浴場へ行った。
入り口には、「大晦日のため本日5時で終了」と書かれた紙が張ってあった。
浴槽からあがると
「父さん、背中擦るよ」
と隆一は言った。
「今日の隆一は煙突掃除は手伝うは、背中は流すは、随分と親孝行だな」
と父は言った。
たくましい父の背中であった。だが、その背は傷だらけであった。
傷口には石炭の粉が入るため、傷跡はイレズミのように黒ずんでいた。隆一はそれらの傷跡を手で確かめるようになぞった。
(こんなにしてまで、俺たちのために働いてくれたんだ。そして・・・)
隆一は父の背中を見ているうちに、涙があふれてきた。
「どうした、隆一、力が入っていないぞ」
隆一は泣いていることを父に気づかれないように、力を込めて背中を流した。
家に帰ると、母は忙しく台所仕事をしていた。テレビの上には、まだ使っていない葉書が何枚か置いてあった。隆一はその中から一枚を手にした。
「母さん、この葉書一枚もらってもいい」
「いいけど。隆一、それを書いたら郵便局へ行って出すんだろう。そしたら、父さんの酒も買ってきてちょうだい」
「うん、わかった」
母にそう答えると、隆一はテーブルに座って葉書を書き始めた。隆一は、ここに来る前の大人の自分に書いていた。いくら気をつけて書いても、子供の文字になってしまうのが、自分でも可笑しかった。
家を出ると、外はもう暗く、街路灯がつけられ、通りは雪明かりで照らし出されていた。人通りが多く買い物をする人たちが行き違っていた。人々が生活する躍動感に、通りは満たされていた。
(やはり、人が行き交うこの街が一番いい)
隆一はそう思いながら、雪を踏みしめ歩いた。
やがて食堂を過ぎると、BARエルボンが見えてきた。
隆一はドアの前まで近づいて行った。ドアには門松が飾られ、一月三日まで休業する旨の張り紙があった。確かに、ここにBARエルボンはあった。
隆一はポストに葉書を投函すると、酒屋に寄り、父の酒を買い求めた。そして、懐かしい街の様子を見ながら、街路灯の下を元来た道へと引き返した。
年越しの夜
七時近くから皆で食卓を囲み、年越を始めた。
母が朝から支度した料理が並べられていた。
茶碗蒸、煮しめ、なますそして、物置で凍られたタコの刺身。シバレタ漬物もあった。
母は用意が済むと道子に、
「レコード大賞入るからテレビつけて」
と言った。
テレビでは、ザ・ピーナッツが「恋のフーガ」を歌っていた。
「この歌もいいね」
母はテレビに合わせ口ずさんでいた。そこには、歌の好きな若々しい母が座っていた。隆一は、パーマーをかけ薄化粧をした母がきれいだと思った。
若くして父を亡くした母は、炭鉱病院の賄をしながら、隆一と道子を育て上げてくれた。
隆一の知っている母は、おしゃれもせずパーマー気のない髪を後ろに束ね、少し背中を丸めている姿ばかりであった。
母にとっても、今が人生の中で一番幸せなときなのかもしれないと隆一は思った。そんな母を見るのが、うれしいような、切ないような複雑な気持ちであった。
父は神棚にお神酒を上げ、拍手を打つと、テーブルに座った。
その夜は、父も母も楽しそうに一級酒を飲んでいた。
レコード大賞は、ブルー・コメッツのブルー・シャトーに決まった。受賞後うれしそうに語っていたフルートを持っている若者は、それから何十年後かに自殺したことを隆一は思い出した。
レコード大賞が決まると、母はテレビのチャンネルを、NHKに変えた。
「レコード大賞は、やっぱりブルー・シャトーだったね」
母は満足そうに言った。
「ブルー・シャトーは、母さんのお気に入りだからなあ」
父も目を細めながら言った。
隆一は、母がときおりブルー・シャトーのレコードをかけていたのを思い出した。もしかしたら、母はブルー・シャトーを聞きながら、父がいた頃の生活を思い出していたのかもしれないと思った。事実、母の遺品を整理すると、ブルー・シャトーのレコードが、家族四人の写真と一緒に大切にしまわれていた。
少し酔いがまわってきたのか、母は鼻歌をうたいながら一旦テーブルを片付け始めた。そうしているうちに、紅白歌合戦が始まった。若き日の宮田輝が司会を務めていた。
母がテーブルに座ると、父はコップを持ち、もう一度皆で乾杯をした。
「隆一、道子、今日は年越だから夜中まで起きていていいぞ」
父は微笑みながら言った。
「今年もこうして、親子四人元気で年越をできるんだから、ありがたいね」
と母も言った。
この夜が、親子四人で過ごした最後の大晦日であった。でも、隆一はそのことを口にすることはできなかった。
「隆一、おまえも来年から中学生だから、11時過ぎたら父さんと一緒に神社へ行って、裸参り見てくるか」
と父が言った。
すると道子が
「ずるい、お兄ちゃんばかり。父さん、道子も連れて行って」
と父にねだった。
「でも、道子、眠くなっても、一人で歩けるか」
「いいよ、道子が歩けなくなったら、兄ちゃんがおんぶしてやるから。だから、父さんいいでしょう」
隆一は、父と母の顔を見ながら言った。
「よし、わかった。道子、いい兄ちゃんいて良かったな」
父は道子の頭をなぜながら言った。
「うん」
道子は、うれしそうな顔をして、隆一を見た。
隆一は、家族四人で過ごした大晦日のことを思い出してみた。だが、父と道子と一緒に神社へ裸参りを見に行った記憶は全くなかった。
やがて紅白歌合戦も終わりに近づいてきた頃
「隆一、外は寒いから、おまえも特別に酒を飲んでみるか」
と父が言った。そして、コップに少しだけ注いでくれた。
隆一は一気に飲んだ。
「あら、おまえも父さんみたいな飲んべになるね。もうエルボンに父さん迎えに行かされないね」
母は目を細め、隆一を見ながら言った。
「そうだな隆一、今度エルボンで一緒に飲むか」
父も笑いながら言った。
「何だかおいしいな。父さんもう一杯だけいい」
隆一がそう言うと、今度は母が注いでくれた。
(ああ、俺はこんなにも、両親に愛されていたんだな)
隆一は、両親に対する感謝の気持ちを伝えたくなってきた。
「父さん、いつも俺たちのために、体に傷つけながら、石炭掘ってくれてありがとう。俺、父さんの仕事って本当に凄いと思っている。母さんもいつもありがとう。俺たち大きくなるまで父さんの分も頑張ってくれて・・・」
そこまで言うと、隆一は急に激しい酔いに襲われてきた。父の顔も母の顔もぼやけ、二重に見え出してきた。
父の声が遠くから聞こえてきた。
「隆一、おまえも母さんのこと支えて、良く頑張ったな。父さんのために苦労かけて、色んなこと我慢させてしまった。父さんは、おまえのこと誇りに思っている・・・」
そして母の声も聞こえてきた。
「隆一、母さんも同じだよ。おまえは本当に良くやってくれたよ。おまえと道子がいてくれたから、母さんはね、父さんの分まで頑張ってこれたんだよ。本当にありがとうね。これからも家族大事にして、道子とも仲良くね・・・」
母の言葉を聞いているうちに、隆一の意識は薄れていった。
「父さん、母さんごめんね。俺、最近墓参りもしていないし、二人の気持ちも知らず親不孝で・・・」
隆一はそう言おうとしたが、もう言葉にすることはできなかった。
葉 書
隆一は目を覚ますと病院のベッドに寝ていた。周りを見ると妻と道子がいた。
「道子どうしてここに」
「お兄ちゃんは、丸三日間昏睡状態だったのよ」
「あなた、何も覚えていないの」
妻はそう言うと事情を説明した。
隆一は12月30日の夜、ススキノの路地裏で凍死寸前の行き倒れで発見された。財布には、BARエルボンの領収書が入っていた。
警察は暴利バーの事件に巻き込まれた可能性もあるため、その店を探し出そうとしたが、該当する店は一件もなかったとのことであった。
隆一は妻から話を聞くと
「みんなにすっかり心配かけてしまったな。道子にも年末年始の忙しい中、ごめんな」
と神妙に言った。
「お兄ちゃん、BARエルボンって、まさか、あの街の店じゃないよね・・・」
道子はいぶかるように言った。
「ごめん道子、何にも覚えていないんだ」
本当のことは、後でゆっくりと道子に話そうと隆一は思った。
「じゃお兄ちゃん、私とりあえず家に一旦帰るから」
道子はコートを手にしながら言った。
「道子、近いうちに父さんたちの墓参りに行こうか」
道子はコートを手にしたまま、一瞬、隆一の顔を凝視して
「うん、私もそう思っていたの・・・」
と答えた。
その日、隆一の家には沢山の年賀状に混じって、色褪せた一枚の葉書が届けられた。
そこには子供の文字が書かれていた。
「今、家に帰っています。ここには、父さんがいて、母さんがいて、道子がいます。まもなく、家族四人で年越が始まります。僕はみんながいてくれてとても幸せです。隆一にもこんなときがあったことを思い出してください」
隆一は、家族四人で過ごした大晦日の奇蹟を、大切に心の中にしまい込んだ。
(2000年 発表)
(筆者紹介)
夕張市鹿島生まれ
生まれてから高校卒業までの18年間を大夕張で過ごす。『ふるさと大夕張』にはしばしば投稿していたようだが、素顔は謎である。札幌在住。










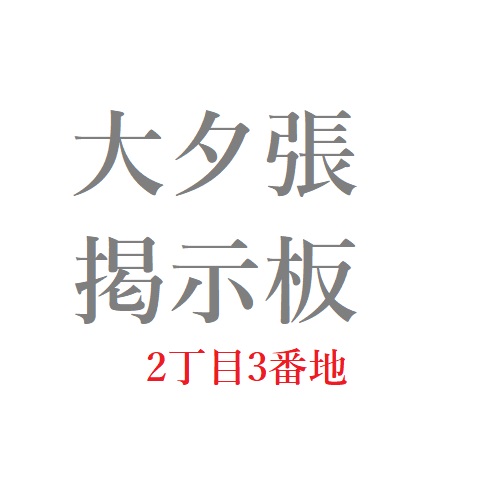










煙突掃除か。長屋に住んでた時に誰とかは忘れたが覚えている。長屋の端に梯子があったのかブラシはどこかにかけてあったのかも思い出せないが、ブラシで煙突をコンコンと叩くと折り返しコンコンと返事を返してくると掃除を始める。何も合図がないと必要なしもしくは留守ということで次に移動する。それにしても小学生の3~4年生がやるかな?