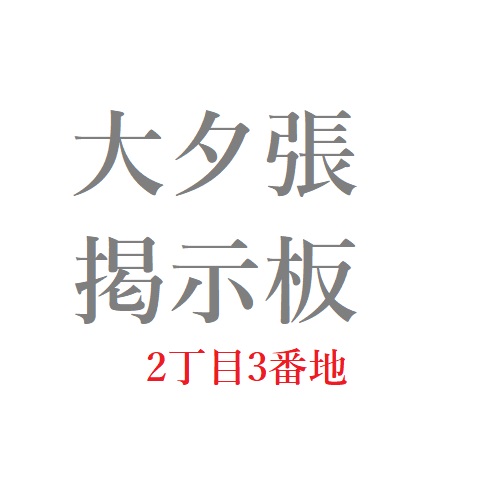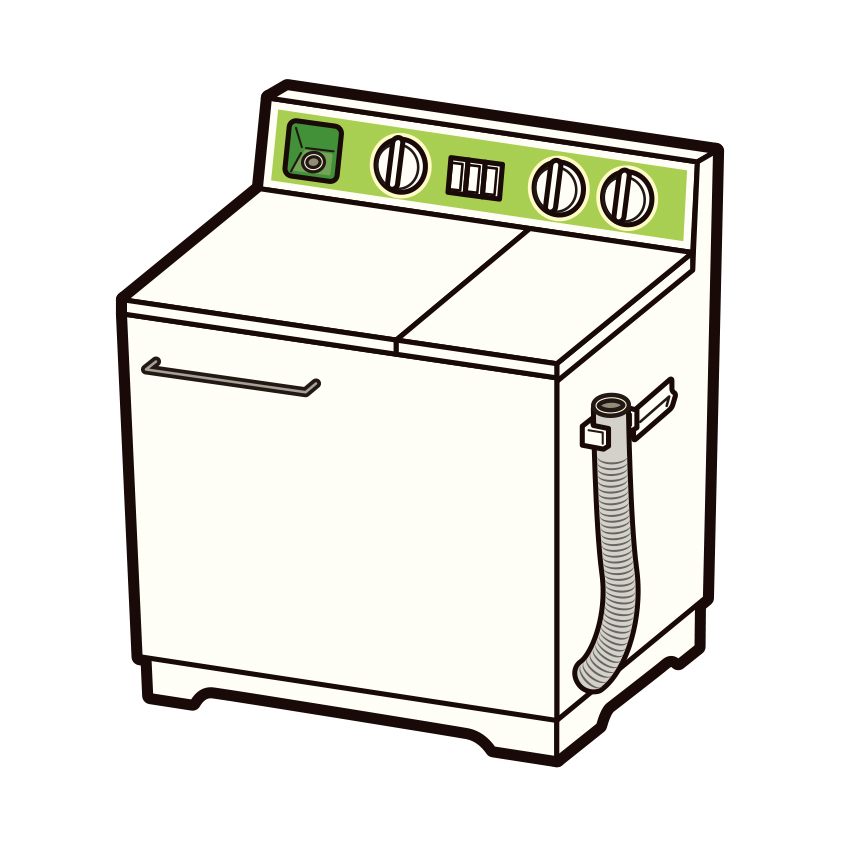バス停 |夕輝文敏

そこには、寝息を立てて横たわっている七二歳の父がいた。
ここが病院のベッドでなければ、まるで安らかに睡眠をとっているかのようであった。
屈強な体で、かつて石炭を掘り続けていた父が、今は病院のベッドの上で生死の境を彷徨っていた。
今朝方、父はスキー場の倉庫で意識不明の状態で発見された。
昨日の夕方頃から父は行方不明になってしまった。妹の恭子のところへも行っていなかった。九時を過ぎた頃、恭子とも相談し警察に届けた。
「兄さん、父さんに何かあったら、どうしよう・・・」
不安そうに恭子が言うと
「大丈夫だよ。親父は元先山やっていたぐらいだから、一晩でどうってことはないさ」
と私は自分に言い聞かすように言った。
あの街の炭鉱が閉山になった後、両親と妹は恵庭に住むことになった。その年の春、地元の高校を卒業すると、私は千葉で働きだしていた。
それから五年後、私は札幌に仕事を見つけ、北海道へ帰って来た。
妹が旭川に嫁いだ後も、両親は恵庭に居を構え二人で暮らしていた。三年前に母を看取った後、父は呆け始めた。
「お父さん、家に来てもらいましょうよ」
そんな妻の思いやりの一言から、父はこの春から私たちと一緒に暮らすようになった。
父は呆けたといっても、今までは徘徊することはなかった。むしろ、昔の記憶は誰よりも確かであった。
父がいなくなった夜、妻はビデオに気がついた。
「お父さん、外に出るまで、このビデオ見ていたみたい」
それは、父が母と暮らしていたころ録画した夕張が舞台になった「幸せの黄色いハンカチ」であった。もう三〇年前の映画であった。
夕方妻がパートから帰ってくると、テレビとビデオの電源が入ったままで、父が消えていた。ビデオを見た後、父は急にどこへ行こうとしていたのだろうか。
その疑問は、翌日警察の事情聴取の後、明らかになった。
父のことをタクシーに乗せてくれた山本さんが、父の様子に異変を感じ、機敏な対応をしてくれたお陰で、父は凍死せずに済んだ。
警察から連絡先を聞き、私は山本さんにお礼を言うべく、タクシー会社へ尋ねて行った。
「年の瀬といいながら景気が悪いもんですから、大通りの辺りで車を待機させて、お客さんを待っていたんですよ。そうしたら、おじいちゃんが同じところ何度も行ったり来たりしていたんで、何か気になってねえ。それで声を掛けてみたんですよ・・・」
山本さんの話によると、父は何かを探しているように、テレビ塔近くのビルの前を何度も行ったり来たりしていた。
山本さんがタクシーを降りて、
「おじいちゃん、何か探しているの」と聞くと、
「三菱バスの停留場が、この間までこの辺にあったのに、見つからないんだ」
と父は答えた。
「三菱のバス停ね。この辺り何年もタクシー流しているけど見たことないな。おじいちゃん、そのバス乗ってどこへ行くのさ」
「大夕張だよ。おっかと子供が俺の帰り待っているから」
父は山本さんの質問に目を細め嬉しそうに答えた。
「そりゃ、早くバス停見つけなくちゃねえ」
山本さんはそう言うと、無線でタクシー会社の運行指令にバス停を探してもらうことにした。それまでの間、外は寒いからと言って、父を車の中に乗せてくれた。
しばらくして会社から連絡が入った。
「おじいちゃん、困ったねえ。三菱のバス停この辺りにはないって。それと、大夕張って、あの炭鉱のあったところかい」
「そうだ。三菱大夕張だ。俺そこで先山で石炭掘っているから・・・」
父は誇らしげに言った。
「そうなんだ。おじいちゃん石炭掘っていたんだ。それなら、うちの運行指令も美唄の出身なんだけど、その大夕張は、もう三〇年も前に閉山になって今は何にもないはずだって言ってたけど・・・」
「閉山・・・あれえ、ついこの間まで、バスに乗って行ったんだけどな・・・」
山本さんは、父とそんな会話をするうちに、家まで送り届けた方が良いと考え、何度も父に住んでいるところを聞いたが答えはなかった。
その内、父は思い出したように、「スキー場まで行ってくれ」と言い出した。そこが家のそばだと、山本さんに言った。方向を聞くと
「あっち」と言って藻岩山の方を指差した。
車の中で、山本さんが炭鉱での暮らしや仕事のことを聞くと、父は嬉しそうに、まるで、今でもそこで暮しているかのように、正確に生き生きと話し出した。父の記憶は完璧であった。
タクシーがスキー場の手前まで来ると、
「この辺でいい」
と言い、父は丁重に山本さんに礼を述べ、料金も支払った。
そこにはもう恍惚としている父の姿はなかった。
「おじいちゃん、タクシー乗りたいときここに電話くれればすぐ来るから。また、よろしくね」
山本さんは父に名刺を渡した。
父が歩き出した後も、山本さんは家に入る父の姿を確認し車を出した。それでも、山本さんは気になり、父のことをスキー場の事務所にも連絡しておいた。
父はビデオで夕張を見ているうちに、昔の時間に引き込まれてしまったのかもしれない。
それで、急に思い立ち、バスで大夕張へ行こうとしたのだと私は考えた。でも、バス停が見つからなかったので、スキー場まで行ったのだろう。
私たち親子四人は、スキー場の近くの住宅に閉山まで住んでいた。あの頃の時間へ迷い込んだ父は、大夕張に一番近い場所を求めて彷徨っていたのだ。
病院へ行くと妹の恭子がいた。私は、山本さんから聞いた話を伝えた。
「そうか。父さん、大夕張へ帰りたかったんだ・・・」
恭子は溜息をつくように言った。
「仕事は大変だったけど、あの頃が、父さんと母さんにとっても、一番思い出が深いのかもしれないなあ」
私も懐かしむように言った。
その夜、私は父に付き添うことにした。
父は集中治療室の隣の病室にいた。 二人部屋であったがもう一つのベッドは空であった。
消灯時間が過ぎたので、隣のベッドに横になった。今日は長い一日であった。体は疲れているのに、頭は妙に冴え寝付くことができなかった。何度も寝返りをうつが、眠ることができなかった。
そんなとき背中越しに父の声がした。
「眠れないのか」
振り向くと、隣のベッドには服に着替えた父が座っていた。そして部屋の明かりをつけながら言った。
「さあ、英男も早くアノラック着て」
父は立ち上がると既に外套を着ていた。
その外套は、昔、父が大夕張で着ていたものであった。さらに、明かりの下で良く父の顔を見ると、それは大夕張にいた頃の、四〇代の顔であった。
私が何か言おうとすると、父は病室のドアに手を掛け、
「母さんと恭子が待っているから、行くぞ」
と私に言った。
私は慌ててコートを着ると、父の後について行った。病院の裏口から外に出ると一本の道がテレビ塔の方へ続いていた。
車も人の往来もない静かな道を父と二人で歩いていた。
「ああ、大通りのバス停まで行くんだなあ」
私がそうつぶやくと
「皆で雪祭り見に来たけど、すっかり遅くなってしまった。明日、英男も恭子も学校あるのになあ」
静けさの中、父の長靴が雪を踏みしめる音が響いている。中学の頃の冬の夜、父が二番方で坑内の仕事から帰ってくるとき、良く聞いていた懐かしい音であった。
やがて、母と妹の姿が見えてきた。妹は中学校の制服にアノラックを着ていた。
「母さん、恭子、すっかり待たせてしまったな」
父は白い息を吐きながら言った。
「なんも。こっちも恭子ともう一度雪像見てきたところだから。ねえ、恭子」
母は笑顔で恭子の顔を見ながら言った。
そこには、まだ30代後半の母が懐かしい緑色のオーバーを着て立っていた。
私たちの傍らには、あの三菱のバス停があった。
間もなく、急行大夕張行と書いたバスがやってきた。バスに乗り込んだのは、私たち親子四人だけであった。運転手さんの顔を見ると、昔お世話になった懐かしい顔であった。
「わあ、今日は私たちだけの貸し切りバスだ」
恭子が嬉しそうにそう言うと、
「本当だね。雪祭りだけの、深夜の臨時便だから、外にお客さんいないんだね」
母も声を弾ませていった。
私も何だか嬉しくて、気持ちが高ぶってきた。
「こうして、四人で札幌まで遊びに来るなんて、何だか懐かしいな」
私がそう言うと、
「そうだな。たまには皆でバスに乗って、こうして、札幌へ来るのもいいもんだなあ」
と父も嬉しそうに言った。
深夜の札幌の街を後に、バスは大夕張へと走り出す。
私たちは、近所の人の話や、学校の話など取り留めのない話をしていた。父も母も恭子も皆がとても幸せな顔をしていた。
「ああ、いいなあ、こうして親子でバカ話できるのは・・・」
私は嬉しそうに言った。
「こいつ、高校生になってから生意気になったなあ。バカ話ときたもんだ」
父はそう言うと、当時テレビではやっていた、プロレスのヘッドロックを私にかけてきた。
「痛いよ、父さん。腕力ではまだまだかなわないんだから」
私は必死に父に抵抗した。
「そうだよ、あんたが何ぼ勉強できたって、それは父さんが命がけで石炭掘ってくれているお陰なんだから。だから、かなうわけないよ。でも、父さんもいい加減にしなさいよ」
当時炭鉱では、かかあ天下の家が多かったが、我が家もそうであった。
「母さん、お腹空いたなあ」
父がそう言うと、
「お握り、沢山作ってきたから、皆で食べるべさ」
母はナップサックからお握りを出し、皆に渡した。
札幌へ行けばいくらでも食堂があるのに、あの頃はどういう訳か必ずお握りを持って行った。食堂といっても、行くところはテレビ塔の上の食堂ばかりであった。
今から思えば、都会の食堂は気後れがして、入ることが出来なかったのかもしれない。
お握りを食べ終わると、バスの窓からは懐かしいシューパロ湖駅が見えてきた。いつの間にか夜も明け、朝の光がさしていた。
「まだお兄ちゃんと私が小学校の頃、父さんと母さんとで汽車に乗ってきたことあったよね。四人でボートに乗って遊んで、昼ご飯は湖畔亭でジンギス汗食べて」
恭子は懐かしそうに言った。
「そんなことあったね。でも、父さん隣のテーブルに佐藤さんが来ると、一緒に飲みはじめ、夕方汽車で帰る頃、酔いつぶれて大変だったよね」
母がそう言うと、
「そうだよ。俺なんか佐藤さんのおじさんと父さんを、かわるがわるかついで駅まで運んでいたんだから」
私は父の顔を見ながら少し意地悪そうに言った。
「いやあ、あのときは悪かった。でも、今日はこうして皆を雪祭りに連れてきたんだからもう、勘弁してくれよ」
父は頭をかきながら言った。
私の父は酒飲みであった。父ばかりではなく、坑夫たちは良く酒を飲んだ。でも、私たち家族は父の酒が好きであった。父の酒はいつも楽しく、笑い声が絶えなかった。
見慣れた故郷の街並みを見ながら、私たち親子四人は笑ったり、冗談を言ったりしながら、バスに乗っていた。本当に、楽しいバス旅行であった。
宝町を過ぎると鹿島小学校の大きな校舎が見えてきた。
「あれが見えると、帰ってきたって気がするね」
母が溜息をつくように言うと、
「そうだな。この学校はここの自慢だからなあ」
父も頷きながら言った。
私と妹の入学式のときは、母と一緒に校門のところで、父に写真を撮ってもらったことがあった。四月だというのに、まだ雪が沢山あって、皆買ったばかりの、真新しい長靴を履いていた。
やがてバスは終点大夕張へ着いた。
父母の後について、私と妹も降りる支度をしていると、
「ここからは、父さんと母さんしか行けないんだ。お前たちは、元いた場所に帰りな。なあ、英男わかるだろう」
父が名残り惜しそうに言った。
私はそのとき、父は母がいる世界へ行くのだと瞬時に理解した。
「英男、恭子、今日はどうもありがとう。皆で一緒にいれて、とても楽しかった。父さんも、母さんも、英男と恭子の親で、本当に良かった。今日は忙しい中、ここまで一緒に来てくれて、本当に、ありがとうね」
母も涙をこらえながら、それでいて、嬉しそうに言った。
「父さん、母さん、おれもとても楽しかった。本当にありがとう。なあ、恭子」
私がそう言うと
「これからも兄ちゃんと仲良く助け合っていくから。雪が解けたら、二人でまたここに来るから。だから・・・」
恭子はそこまで言うと言葉をつまらせ泣き出した。
私は、恭子の手をぎゅっと握ると、深々と二人に頭を下げた。そして、涙が止め処もなく流れ出した。
両親は静かにバスを降りた。
傍らには三菱バス大夕張と書かれたバス停がしっかりと立っていた。
やがてバスは、大夕張駅の前で旋回すると、静かに走り出した。
二人は、あの懐かしい大夕張の街並みと一緒に、笑顔で私たちを見送ってくれた。
妹と私は泣きながら、二人の姿が見えなくなるまで、手を振っていた。
「父さん、母さん」
私は自分の大きな声で目を覚ました。いつの間にか寝入っていた。今見たのは夢だった。でも、それは、あまりにも、暖かくて切ない夢であった。
その日の夕刻、父は最期に、
「皆で、大夕張さ、帰るべ・・・」
と私と恭子に言うと静かに息を引き取った。
とても安らかな顔で、父は大夕張へと帰って逝った。
(2004年 発表)
(作者紹介)
夕張市鹿島生まれ
生まれてから高校卒業までの18年間を大夕張で過ごす。『ふるさと大夕張』にはしばしば投稿していたようだが、素顔は謎である。札幌在住。