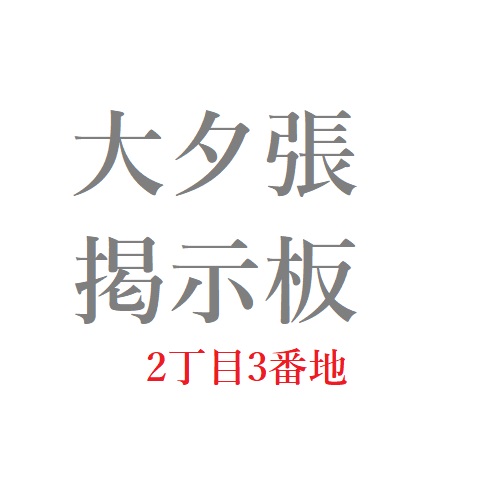タイムカプセル |夕輝文敏

西暦2050年、夕張岳の麓に新しい街ができはじめた。
90年も前に、かつて炭鉱で栄えたように、再び原野に街ができた。
街の名は、大夕張と呼ばれていた。
2000年代前半、未曾有宇の原油高騰と地球環境問題が切迫する中、代替エネルギーとして、石炭が注目された。政府が夕張で試験的に進めていた、かつての石炭層に二酸化炭素を封じ込める実験中に事故が起き、その偶然の産物として、液状化した石炭が産まれた。
専門機関で分析してみたところ、石油の代わりに使えることがわかった。驚くべきことに、二酸化炭素の排出量は、石油に比べ20分の1以下であり、熱効率は10倍以上であることがわかった。
この二酸化炭素についても技術開発により排出量を0にすることができた。コスト的にも、新たに坑道を掘削する必要はなく、前世紀に掘削された旧炭鉱時代の坑道をそのまま活用することができた。
大夕張が蘇ったのには、もう一つの偶然があった。
本来であれば、国のダム事業により水没するはずであったが、ダムの堤体工事中に大きな地震が起きた。ダムの地下深くに、未発見であった活断層が横断していることが明らかになった。
このため政府機関内で検討した結果、国の財政事情もあり、ダムの建設は中止になった。そして、かつての炭鉱街の繁栄を示す全ての建物が解体された後の、原野だけが残った。さらに、繁次郎の沢と呼ばれていた地層から、この地震によって温泉が湧き出た。
液状化石炭の実用化が計られた2040年代から、夕張は急速に栄えだした。
前世紀の石炭産業の衰退により萎んだ街は、新エネルギー革命により、隆盛を極めだした。
皮肉な歴史のいたずらである。人口も増え出し、企業進出による社宅の建設、学校等の公共施設の拡充も計られた。
しかし、かつて赤字再建団体で苦しんだ夕張市は、ハコ物作りはできるだけ押さえ、青少年の教育施設の充実、エネルギー研究機関の誘致、自然との共生を街づくりの基本に据えていた。
すでに市内には、二つの大学、12の研究機関が集まっていた。
「シュン、夏休みはどうするんだ」
父は仕事から帰ってくると、タオルを用意しながら言った。
「うん、今年はリョウたちと、キャンプに行こうと思っているんだ」
「キャンプってあの、白金の沢か」
「そうだよ。でも、天気が問題だなあ。どうせなら、星を見たいからね」
シュンは少し心配そうに言った。
「あそこの星空はすごいらしいなあ。お父さんも一度見に行きたいものだけどなあ」
父はそう言いながら、ドアの前に立った。
「じゃ、お父さんスパへ行って来るから、お母さんも、もうじき学校から帰ってくるから、留守番頼むなあ」
「うん、わかっている」
シュンはそう言いながら、父を見送るとドアを閉めた。
母は、地元の小学校の教師をしているが、夏休み前は仕事が忙しく、ここのところ帰りが遅い。
シュンの父は、エネルギー会社の技術者で、5年前からこの街で働いている。
社宅にはもちろんバス、シャワーはついているが、繁次郎の沢から曳いた温泉で従業員と家族用にエステック施設やスポーツジムを兼ねた大きなスパが作られていた。
夕張市は、旧炭鉱時代の教訓から、社宅の広域分散を避けるため、高層アパート式の社宅を、栄町と富士見町に集約した。
それぞれの社宅には太陽パネルが設置され、一般家庭の電力は、この太陽光と雪によって賄われていた。雪もここでは重要な自然エネルギーとなっていた。
かつての炭鉱は、事故も多く人命が奪われることも多かったが、今は、産業ロボットが坑内作業を行っている。
坑内といっても、石炭を採掘する必要はほとんどなく、かつての坑道に二酸化炭素を注入し、化学反応を誘導するだけで良かった。
後は、パイプラインが、液状化した石炭を吸引するだけであった。それらをプラントでクリーンエネルギーに生成するのであった。
この街が選ばれたのは、石炭の埋蔵量が豊富であり、かつての坑道も南部地区と貫通しているためであった。
さらに地形的にも平地が多く、生産設備、社宅等の立地に適していることであった。
8時前に母も帰宅し、家族がそろい夕食が始まった。
父と母と俊一の3人家族であった。この時代、ほとんどの家庭は子供は3人ぐらいが普通であった。クラスでも一人っ子はシュンのところだけであった。
環境問題の改善とあわせ、人口も増加に傾いていた。
「シュンは夏休み、白金の沢にキャンプに行くそうだ」
父はビールを美味しそうに飲みながら言った。
「リョウ君たちと行くの」
母もビールを飲みながら言った。
「うん、リョウとヒデと3人で行くんだ」
「あんたたちは、小学生の頃からいつも一緒で仲が良いのね」
母は微笑みながら言った。
「だって、最近色んなところから人がやってきて、生徒増えているけど、やっぱり地元っ子の方が気が合うんだよなあ」
シュンはまじめな顔をして言った。
「ほお、地元っ子ね」
父は笑いながら言った。
「そうだよ。俺たち岳見小学校4年生のときから、ずっと一緒だからね」
シュンは自慢そうに言った。
「そうだよね、今は石炭景気で、人口が増え続けているし、夏休み明けにまた何人か転校してくるって言うし」
「そんなに生徒が増えて、学校大丈夫なのか」
父がそう言うと
「市の方でも、校舎の増築を計画しているみたい。ここのリゾート計画も大当たりだしね」
と母は答えた。
エネルギー会社は、温泉を利用して、シューパロ川に接している春日町に長期滞在型の保養施設を作った。
豊かな自然環境を生かし、昭和の頃の炭鉱長屋をイメージしてコテージを建てたところ、大変な人気を呼んだのである。もちろん設備は最新であるが、基本設計は長屋を忠実に再現していた。
「お父さん、夏休みにはおじいちゃんが遊びに来るって言ったよね」
「そうだな、この間電話で言っていたなあ」
「じゃ、キャンプの日決まったら、かち合わないように連絡しなくちゃね」
「私も、その日は登校日にぶつからないようにしなくちゃ」
「そうだね、みんな、ありがとう」
父はうれしそうに言った。
「おじいちゃんとこの車庫に、まだガソリン車あるのかなあ」
シュンは思い出したように言った。
「ガソリンなんてもう売っていないのになあ。きっと、おじいちゃんの大切な思い出が沢山詰まっているんだろうなあ」
父は子供の頃の家族でのドライブを思い出しながら言った。
この時代、ガソリンで走る車はもう生産されていなかった。
かつての富裕層がいた産油国も、今では、クリーンエネルギーの輸入国になっていた。日本は、石炭と自然エネルギーの活用により、エネルギーの自給率も90%に達していた。車も暖房も二酸化炭素ゼロの液状化石炭によって賄われていた。
シュンのおじいちゃんは、かつて小学生3年生まで、この街で暮らしていた。シュンたち一家がこの地にやって来てからは、足繁く通ってくるようになった。
白金の沢には、市営の青少年向けのキャンプ場が作られていた。
周辺には清流が流れており、夏には近隣の市町村の学校からも子供たちがやってきた。
この施設には、ルールが一つだけあった。
それは、PTAの同伴を認めず、子供たちだけで宿泊することであった。
ここには、プロ集団を始め、多くのボランテイアのスタッフも配置されている。キャンプ場までは、市のスクールバスが送迎をしていた。
夕張市は、青少年の育成には力を注いでいた。
この地で育った子供たちは、一度は都会へと羽ばたいて行く。そして、いつか帰ってきたくなったら、仕事と住むところを斡旋し定住化を進める。
新石炭産業による就業人口への需要が、その政策を裏付けていた。何世代にも渡り夢見ていたことが、今の夕張では実現することができる。
夏休みに入ると、シュンたち3人は、白金の沢キャンプ場にやって来た。
「中学2年生って、俺たちだけかな」
キャンプ場に着くなり、リョウが言った。
「服装次第で、大人びて見えるんだよ、ビビるなよリョウ」
ヒデは冷やかしながら言った。
「俺は別にビビッていないよ」
リョウは少し口を尖がらせながら言った。
「何言ってるんだよ、お前らは。そういえば、こうして3人だけで泊まるなんて、小学校の宿泊学習以来だよな」
シュンが言うと2人とも頷いた。
小学校5年生の秋に、春日町のコテージで宿泊学習あった。
仲の良かった3人は、同じ長屋の部屋に泊まった。炭鉱長屋もめずらしく、3人にとっては忘れられない新鮮な体験であった。
川の音を一晩中聞きながら、話が弾んだ。
(昔ここに住んでいた人たちも、こうして川の音を聞きながら暮らしていたのかなあ)
3人は同じことを考えていた。
そして、今のような暖房設備もない、羽目板式の家で、ここの冬を乗り切ったのだから、昔の人は、大人も子供もすごいと感じていた。
でも、この長屋はとてもどこか暖かいと思った。まるで建物自体がみんなを包み込んでくれるような、不思議な感覚であった。
3人は管理人の許可を得ると、テントを借りた。
「どの辺にテントを張ろうか」
ヒデが言うと
「え~と」
と3人で周囲を見渡し、適当な場所を探した。
「あの木の下がいいや」
そう言うとリョウは、カエデの大きな木の方へ走り出した。
そして、リョウとヒデを呼び寄せた。
「うん、ここがいいや」
ヒデも満足そうに言った。
3人はもう一度下から木を見上げると、木はまるで3人を待っていたかのように、凛として枝を張っていた。それでいて、どこかほっとするような穏やかさを漂わせていた。
初めて来た場所なのに、3人とも何か懐かしいものを感じていた。
夕食は、スタッフの指導の下に、バーベーキューを楽しんだ。
このキャンプ場には小学生以上であれば、参加することができた。
生徒の学年人数によって、ボランテイアを含めスタッフが配置されていた。
日が沈むと、夕闇が徐々に迫ってきた。各ブロックごとに、キャンプファイヤーが用意された。
シュンたちは、いくつかのゲームに参加した後、9時ごろにテントに戻ってきた。
3人は空を見上げた。満点の空に星が散りばめ輝いていた。こんなにも沢山の星空を見るのは、初めての体験であった。
「すごいなあ、この星・・・」
リョウは思わずため息のようにつぶやいた。
シュンもヒデも感動に包まれていた。
「星ってすごいんだ。今見えている星のほとんどは、何十年いや何百年もかかって、やっと地球まで光が届いているんだ」
シュンは星を見上げたまま言った。
「そうそう、それって光年って言うんだろう。100光年だと、100年前の光が今ここに届いて、俺たちが見ていることになるんだ」
ヒデも言った。
「それって、俺たちのおじいちゃんのもっと前のおじいちゃんが生まれたころの、星もあるってことだよなあ」
3人は、それぞれの話にうなずきながら、飽きることなく星を見ていた。そのとき、夜空にひときわ赤く輝く星があった。
「おい、あの星を見ろよ」
とリョウが指をさして言った。
すると、3人が見ている間に、白く光り輝いたかと思ったら、一瞬のうちに消えてしまった。
「どうしたんだろう」
ヒデは不思議そうに2人の顔を見て言った。
「あの星は今爆発して、宇宙の塵となって、消えてしまったんだ。でもその今というのが、本当は何百年も前のことかもしれないんだ。こんな瞬間を見れるなんて、本当にすごいことなんだ」
シュンは興奮しながら2人に言った。
3人はそれからもしばらく消えた星の方を見ていた。
3人はテントの中に入っても、夜が更けるまで学校のことや家族のことなどについて話していた。そして、話し声はいつの間にか寝息へと変わっていた。
シュンは夢を見た。
この白金の沢に10人ほどの子供たちがキャンプに来ていた。テントはどれも、今まで見たこともない古臭い三角テントであった。その一つには文字が書かれていた。よく見ると「夕張市立鹿島中学校」と書かれていた。
(鹿島中学校ってどこにあるのだろう)
シュンはそう思いながら見ていた。
中学生らしい子供たちは、今ではあまり見かけない服装をしていた。
その中から、男の子2人女の子1人の3人が手前のカエデの木の下にやって来た。
「いいか、これから一人ずつ、この木の下にタイムカプセルを埋めるんだ。そして、そうだなあ、10年後にまたここに来て、掘り出すんだ」
一番体の大きな男の子が言った。
「でも、この入れ物で大丈夫なのかな」
もう一人の男の子が不安そうに言った。
「大丈夫だよ、このタッパウエアーってアメリカ製で一度ふたをすると、絶対に空気がもれないんだって。だって、1個800円もするんだから」
しっかりした声で女の子が言った。
それから男の子たちは交代で穴を掘り始めた。その間女の子は弁当箱ぐらいの入れ物を3個大事そうに胸に抱えていた。腰の辺りまで掘り進むと、入れ物を受け取った。
「あっ、そう言えばトシヒデ、アキオ、手紙の最後に今日の日付ちゃんと書いたでしょうね」
と女の子が言った。
「あっ、忘れた」
と男の子たちは、大きな声で同時に言った。
「でも大丈夫、ミヨコはちゃんと書いたんだろう」
と大きな体の男の子が言った。
「そうだよ。どうせ掘り出すときは3人一緒なんだから。ミヨコ書いたよなあ」
ともう1人の男の子が言った。
「当たり前でしょう。昭和42年、1967年7月28日ってしっかり書いたわよ」
女の子は少し怒ったような声で言った。
「よっ、さすが加藤さん家の長女、しっかり者」
男の子たちははやし立てるように言った。
土を埋め戻すと3人は楽しそうに笑いながら立ち去った。そして、もう一度カエデの木を振り返った。そのとき、シュンは一瞬3人と目が会ったような気がした。
雨の音で目が覚めた。
昨夜はあれほど天気が良かったのに、雨が強く降っていた。時計を見るとまだ、4時を少し過ぎたばかりであった。シュンは雨の音を聞いているうちに、再び眠りに落ち夢を見たことなど忘れてしまった。
3人はここに2泊し、キャンプを楽しみ、家路に着いた。
シュンはその日の夕食のとき、父と母にあの星空の素晴らしかった事を話した。
「そんなにすごいなら、お父さんも一度見に行きたいなあ」
と父が言った。
「お母さんも見たい」
と母も言った。
するとシュンは
「二人で行ってくれば」
と言った。
父とは母二人で顔を見合わせると笑い出し
「それでは遠慮なく二人で行かせていただきます」
と母が言った。
その夜、シュンはまたあの夢を見た。古い三角テントから、あの3人が出てきて大きなカエデの木の下にタイムカプセルを埋める夢であった。
次の午前中、両親が仕事に出た後、リョウとヒデがやって来た。3人が集まる時は、兄弟のいないリョウの家に自然に集まるようになっていた。
リョウは入るなり
「俺、思い出したんだけど、キャンプした最初の晩夢見たんだ。中学生が3人、それもかなり昔の中学生なんだけど、男の子が2人と女の子が1人いて、大きな木の下にタイムカプセル埋めるんだ」
と少し興奮気味に言った。
「古臭い三角テントが四つあって、その一つには、夕張市立鹿島中学校って書いてある」
シュンも興奮して言った。
「まさか、タッパウエアーのそう弁当箱ぐらいのタイムカプセルじゃないよなあ」
とヒデが少しおどけて言った。
「そう、そう、そのタッパウエアーだ。3人の名前は、男の子がトシヒデとアキオで、女の子がミヨコ」
リョウも大きな声で言った。
「俺、元々ボーっとしているから、この熱さで頭がおかしくなったのかと思ったら、リョウもシュンも同じ夢を見ていたんだ。そして、まさか、夕べも見たなんて言わないよなあ」
ヒデが二人の顔をまじまじ見ながら言った。
「おまえたちも、見たのか」
シュンとリョウが同時に言った。
「よし、学校へ行こう。図書館で調べてみよう、その鹿島中学校について」
シュンは2人を促すかのように言った。
3人が通う岳見中学校は、代々木町にあった。
今は街の人口も1万2千人に達していた。
1学年5クラスの中学校であった。小学校は、昔炭鉱時代に建っていた同じ場所に建てられ、岳見小学校と呼ばれていた。この街のどこからでも前岳に被さった夕張岳を見ることができるので、「岳見」と名づけられた。
「あった、あった鹿島中学校。この学校って昔の炭鉱時代にあった中学校だ。そういえば郷土史で勉強したけど、この時代は、小学校も中学校も沢山あったからな。名前までは覚えきれないんだ。でも、鹿島中学校は、3人がいた頃は3学年で26クラスもあったんだ。大きな中学校だったんだ」
リョウが資料を見ながら言った。
「じゃ、俺たちの先輩みたいなもんだ。1967年て、ええっと、今から83年前だよなあ、すごいぞ、こりゃあ」
シュンも頷きながら言った。
「そんな大昔なら、今頃3人とも、もうナンマイダかなあ」
ヒデがおどけながら言った。
「ばか、何てこと言うんだ」
リョウはヒデの頭をポカンと叩きながら言った。
「いてえなあ、あっつ、ちょっと待てよ、1967年7月28日だよなあ、タイムカプセルを埋めた日は。それって、俺たちがあそこでキャンプした日だよ」
ヒデはまじめな顔で言った。
「本当だ、ヒデすごいなあ。こんな当たり前のことに今まで気がつかなかったなんて」
シュンがそう言うと
「そこが、君たち二人のまだ未熟なところなんだよなあ」
とヒデは得意そうに言った。
「でも、不思議だよなあ、あの夢。何か懐かしくて、ほっとするって言うか。俺あの夢好きだなあ」
リョウは想いをこめてそう言った。
「俺も、同じ気持ちなんだ」
とシュンも言った。
「俺もだよ」
少し遅れてヒデも言った。
その日3人は、いつまでもこの街の歴史について調べていた。
次の日の午後、シュンのおじいちゃんが尋ねてきた。
「急に、夕張メロンの地物が食べたくなってなあ」
おじいちゃんは、箱一杯に入ったメロンを抱えながら家に入ってきた。
「しかし、ここも随分と建物も増え、人も入ってきたなあ」
シュンの家の10階のベランダから街を見ながら、おじいちゃんは言った。おじいちゃんは、子供の頃の原野だらけの街の姿を重ねていた。
その夜、夕食が始まると、シュンは少しかしこまりながら言った。
「あのキャンプの夜から、俺たち不思議な夢を見ているんだ・・・」
シュンはみんなにあの夢の話をした。そしてリョウたちと図書館で鹿島中学のことや街の歴史についても調べたことを話した。
「あら、大夕張のことなら、おじいちゃんが詳しいのに」
と母は言った。
「そうだよ、おじいちゃんは昔ここにあった鹿島小学校の最後の在校生だっただから」
と父も言った。
「えっつ。おじいちゃんは夕張たって本町の小学校とばかり思っていたけど」
シュンは意外な顔で言った。
「しょうがないよ、シュンがそう思うのも。実際大夕張は夕張の歴史の中では、一度は消えてしまったんだから。それどころか、本当はダムに沈む運命だっただから」
おじいちゃんは、そう言いながら原野になった街には大きすぎる校舎の姿を思い浮かべていた。
「おじいちゃん、鹿島中学のこと覚えている」
シュンは目を輝かせながら言った。
「おじいちゃんが小学校に入ってすぐに、中学校は閉校になってしまったんだ。中学たって、当時は小学校と同じ建物で、そうだなあ、生徒も7、8人ぐらいしかいなかたんじゃないかな」
「そうか、最後は小学校に吸収されていたんだ」
シュンは残念そうに言った。
「シュン、今の岳見小学校には、大きなイタヤカエデの木があるのを知っているね。 あの木は300年も生きているんだ。 この大夕張の歴史を過去にいた人々の生活など、色んなことを全部見守ってきたんだ。 あの木には、この大地の神様が宿っていると、おじいちゃんは思っている。 人々の記憶が染み付いているこの大地の神様が、シュンたち3人を選んだのかもしれないなあ。 それって、とっても素晴らしいことだとおじいちゃんは思う」
おじいちゃんは、そう熱を込めて言った。
「大地の神様か。あの木にも宿っていたのかなあ」
シュンはどこかで納得できる気持ちで、おじいちゃんの話を聞いていた。
それから3日後に、また3人は同じ夢を見た。
「これはもうただの夢ではない。あのタイムカプセルの場所を探し出して、俺たちで掘り出してみよう。なあシュン、ヒデ」
リョウがすこし高ぶる感情を抑えながら言った。
「探し出す必要はないさ。俺たちがテントを張った、あの大きな木だよ、きっと」
ヒデはニヤリとしながら言った。
シュンはおじいちゃんから聞いた 「古い木には、大地の神様が宿る」 という話を2人にした。
「大地の神様か。あの場所にも昔から沢山の子供たちがキャンプをしたりして遊びにきたんだろうなあ。俺たちがあそこにテントを張ったから、あの木も昔のことを思い出して、俺たちに夢で語りかけてきたのかなあ」
ヒデは、まじめな顔で言った。
「ヒデのいうとおりかもしれないなあ」
リョウもうなずきながら言った。
次の土曜日、シュンの父の車に乗って、3人はキャンプ場に向かった。
父は管理人に事情を話し、掘削の許可を得た。管理人も話しに興味を示し、一緒にカエデの木のところにやって来た。
「シュン、どこを掘ればいいんだ」
父はシュンたち3人の顔を見ながらに言った。
リョウは少し考えてから、川に面しているこの場所で間違いないと言った。
シュンもヒデもうなずいた。
最初にリョウから掘り出した。3人は「これは俺たちの仕事だから」と、大人の助けを借りずに掘ることにした。
夢に出てくる穴は、中学生達の腰の辺りの高さであったが、3人はそれより深く掘り進んだ。1mぐらい掘ったが何も出てこなかった。
「よっし、もう少し範囲を広げて掘ってみよう」
リョウはそう言うと違う場所を掘り始めた。
それから1時間ほど掘り進んだが、ここも何も出てこなかった。
「本当にこの木で間違いないのか」
シュンの父が少し遠慮がちに言った。
「この木で間違いないよ」
3人は同時に答えた。
「問題は方角だ。よく思い出すんだ。枝の形とか何か目印はなかった」
リョウは2人に言った。
「あっ、そうだ。1本だけ横に少し曲がって伸びている枝があった。その下を掘っていたんだ」
シュンは思い出して言った。
それから、3人はもう一度じっくりと木を見渡した。するとヒデが言った。
「あった、この枝だよ。あれからだいぶ大きくなったけど、この曲がりは間違いない。ここを掘ってみよう」
3人は1mほど掘り進むと、スコップは何かにぶつかった。それから先は傷つけないように、慎重に掘り進んだ。
そして、遂にタイムカプセルを掘り出すことができた。
新聞紙らしいボロボロになった紙を取り除くと、3つの弁当箱ぐらいの大きさの容器が出てきた。どれも色はくすんでいたが、どこにも損傷はなかった。
「やっぱりあったんだあ。3人のタイムカプセルが」
ヒデはスコップを置くとそう叫んだ。
「やった、やった」
3人は喚声をあげた。
側で見ていたシュンの父も管理人も、手を取り合って喜んだ。
その後管理人の好意により、事務所にタイムカプセルを持ち込んだ。そして、開けてみることにした。
「ちょっと待って。あのとき、10年後に集まって3人で掘り出すって言ってたけど、3人はここにももう来なかったのかなあ」
シュンがそう言うと
「ここで開けるのはよそう。やっぱりあの3人に返さなくちゃ」
とリョウも言った。
「そうだ、3人を探そう」
とヒデも言った。
側ではシュンの父もうなずいて聞いていた。
3人はもう一度鹿島中学校のことを調べ始めた。調べれば調べるほど、大夕張地区のかつての繁栄を知ることができた。
「1967年昭和37年には、鹿島中は生徒数1661人、34学級で最大規模だったんだ。岳見中学が3学年15クラスだからすごいな」
リョウが言った。
「シュンのおじちゃんは、昔鹿島小学校にいたんだから、中学校のことも知っているんだろう」
何気なくヒデが言った。
「だめだよ、じいちゃんがいた頃には、もう中学校は閉校した後だって」
シュンは残念そうに言った。
「おい見ろよ、鹿島中学って、こんな遠いところにあるぜ。みんなどうやって通学していたんだろう」
リョウが言うと
「お母さんに聞いたんだけど、昔は小学校の建物の中に中学校もあったんだって。でも生徒が増えて中学校を新しく建てるとき、今のコテージのような炭鉱長屋が、平地という平地に一杯あって、遠いその場所にしか土地がなかったらしいんだ。だから、みんな歩いて通学したらしい」
とシュンが言った。
「えっ、昔の中学生ってタフだなあ。ここからだったら、片道だけでも40分ぐらいもかかるなあ。岳見中なら5分ぐらいで行けるのに」
ヒデは感心しながら言った。
「見ろよ当時の人口1961年には、南部を含めた大夕張地区の人口が23751人もいたんだ。今から90年前には、大きな街だったんだなあ」
リョウは資料を指しながら言った。
「今の大夕張が12000人だから、すごいなあ」
新エネルギー革命により、夕張市の人口は8万人に膨れあがっていた。
シュンたちは、こうして何日か図書館に通ううちに、およそ100年前の炭鉱町としての大夕張の姿がつかめてきた。
しかし、卒業生の名簿については探し出すことができなかった。それらは、夕張市の教育委員会にあることがわかった。
岳見小学校の教員であるシュンの母と一緒に3人は教育委員会を尋ねることになった。
教育委員会では、シュンたちの話を聞き終わると、快く協力することを承諾してくれた。
「かつて石炭を掘ってくださった先人の労苦があればこそ、今日の夕張の繁栄があるのですから、是非この3人を探し出しましょう。市役所にも協力してもらえるように、こちらからも頼んでみましょう」
と事務局の人も言ってくれた。
それから数日後、遂に名簿が出てきた。
1969年、昭和44年3月12日卒業第22期生の中に3人の名前はあった。「大久保 俊英」「田村 明夫」「加藤 美代子」の3名であった。
「まだお元気なら3人とも今は97歳ぐらいですな。何とかこのタイムカプセルを渡せるといいですね」
作業を見守っていた教育委員会の委員長も、いたわるように言った。
「ここまできたんだから、何としても3人に会いたいなあ」
リョウもうなずくように言った。
「何か、今年の夏休みってすごい夏休みになったなあ。まるで、俺たちがタイムカプセルを埋めたような気がしてきたよ。俺、この夏休みは、一生忘れない」
ヒデも考え深そうに言った。
「ヒデ、今のせりふ決まってるな」
とリョウがまじめに言うと
「この夏休みは、一生忘れないときたもんだ」
とシュンも言い出すと、3人は笑い出した。
シュンたちは、それからも図書館で、前世紀の街の歴史を調べた。そして、色んなことがわかってきた。
今の南部で石炭の大露頭が発見されたのが、1888年(明治21年)で、1906年(明治39年)には、炭鉱事業が開始されたこと。
1909年(明治42年)頃から今の南部が大夕張と呼ばれだしたこと。
当時今の大夕張は「北部大夕張」と呼ばれ、1927年(昭和2年)に開発が行われた。
翌1928年に、「官行」「富士見町」「栄町」「千年町」ができた。
1929年(昭和4年)に、三菱鉱業大夕張鉱業所が南部から北部大夕張に移転。この年、駅名も、大夕張駅が南大夕張駅に北部駅が大夕張駅と改称し、今の大夕張となった。
1955年(昭和30年)10月1日、国勢調査で鹿島地区が最高の18778人を数える。
この年夕張市の人口が、107332人で、南部を含めた大夕張地区が22594人となる。
1973年(昭和48年)6月30日大夕張炭鉱閉山決定。1998年(平成10年)国のダム建設による移転により、ついに人口が0となる。
「二股の大露頭発見から、ダムの移転により人口が0となるまで、110年の歴史があったんだな。今からだと、石炭の発見は162年前になるんだ」
シュンは感心しながら言った。
「人口が一番多かった1955年には、小学校が二つと中学校が一つあったんだ」
リョウもノートを見ながら言った。
「3人がキャンプをした1967年は、夕張市の人口も10万を割り81435人で鹿島地区が12871人になっている。この年は、鹿島中学校の開校20周年の記念事業も行われているんだ」
ヒデも感心しながら言った。
3人は調べれば調べるほど、前世紀の炭鉱時代には、この地に沢山の人々の長い歴史が刻み込まれていることを、感ぜずにはいられなかった。
夏休みが終わりに近づいた頃
「シュン、あの3人のことがわかったよ。みんな札幌の同じ老人介護施設にいるのよ」
母は夕張市が調べてくれた内容について話した。
3人はともに1953年生まれで、18年間地元の高校を卒業するまで、この街で暮らしていた。3人が就職、進学で街を出た翌年、炭鉱が閉山になってしまった。その後それぞれの人生を歩み、今は3人とも同じ施設で生活しているとのことであった。
「シュン、これからどうする」
母はシュンの顔を見ながら言った。
「まずこのことをリョウとヒデに教えなくちゃ。それとおじいちゃんにもね」
リョウたちは学校の図書館にいた。
「3人とも97歳になっても一緒に暮らしているんだから、何かすごいなあ」
リョウは少し感動しながら言った。
「よし、すぐに会いに行こう。そしてタイムカプセル渡さなくちゃ」
ヒデもすぐにそう言った。
「お母さんに言われたんだけど、まず今回のことを施設の人に話して、会いに行っていいかどうか3人の気持ちを確認するのが先だって」
シュンは2人に言った。
「タイムカプセル持って会いに来てくれって言うに決まってるさ」
リョウは当然のことのように言った。
「だといいけどなあ。もし、会いたくないって言われたらどうしよう」
ヒデは少し不安そうに言った。
「とにかく教育委員会の人たちが、3人に連絡してみるって。それからだよ、なあ」
シュンがそう言うと2人ともうなずいた。
その日の夕方、食事をしていると、おじいちゃんからシュンに電話があった。
「シュンから聞いた3人のうち、田村明夫さんのことだけど、おじいちゃん思い出したことがあるんだ」
「えっ、おじいちゃん、田村さんのこと知っているの」
シュンは驚いたように言った。
「おじいちゃんの小学校は生徒が12名になったとき閉校になったことは話したね。 そのときの閉校式は、1997年6月に行われたんだ。 そのときは本当に沢山の人が集まってきてなあ、まだ小学校の3年だったけど、子供心にも、強い印象を受けたもんだ。 体育館で式典が終わると、集まった人たちが卒業年次ごとに、記念写真を撮っていたんだ。 そのとき、偶然おじいちゃんの側にいた女の人が1人、男の人が2人のグループから、シャッターを押してくれるように頼まれたんだ。 そのカメラは当時としてはまだ珍しいデジカメだったから、おじいちゃんよく覚えていたんだ。 そして、記念だからといって、今度はおじいちゃんも一緒に4人で写真を撮ったんだ。そして必ず送るからといって、住所を聞かれたんだ。 後で写真はちゃんと送られてきたんだ。 そのときの差出人が田村明夫さんだったんだよ。 すっかり忘れていたんだけど、シュンから話を聞いた後、何か引っかかるものがあって、そのときの閉校記念誌(かしま)を出してみるとその写真が一緒に挟まっていたんだ。それではっきりと思い出してなあ。そうそう、もう1人の男の人がおじいちゃんにこんなことを言ったんだ。
(君たちはたった12人の生徒ではない。この歴史ある鹿島小学校の卒業生9790名の代わりに、最後を見送ってくれた12人もの生徒なんだ。だから胸を張って誇りを持つんだ)
確かこんなあ感じだったなあ。そのとき、おじいちゃんも何かとってもうれしくなったことを今でも覚えているよ。だから、おじいちゃんも、あの3人に一緒に会いに行きたいと思って」
シュンはおじいちゃんの話を聞きながら、これはすごいことになったと思っていた。
8月最後の日曜日、シュンの母の運転する車に乗り、札幌に向かっていた。あの3人は大倉山の麓の高台にあるレンガ造り風の建物に住んでいた。周囲を沢山の木々に囲まれ、バルコニーからは、札幌の町並みを一望することができた。
車が駐車場に入ると、おじいちゃんは先に来ていて車の中で待っていた。車を降りると、母はすぐに受付に行き用件を伝えた。そして、シュンたちは応接室に通された。
「ついに、ここまできたね。シュン」
母がシュンの肩に手を置き言った。
「うん」
シュンがそう言うと、おじいちゃんと一緒に目をあわすと、みんなうなずいた。
やがて、スタッフの人が1人の老人を車椅子に乗せ、部屋に入ってきた。
その後から杖をついた二人の老人が入ってきた。そのうちの一人は、すぐにミヨコさんだとわかった。髪をきれいな栗色に染め、化粧をほどこし、どことなく粋な感じのする人であった。
「どうも、お待たせしました。わざわざお越しいただいて、ありがとうございます」
車椅子に座った老人がしっかりとした声で言った。
その後に二人の老人も同じように
「わざわざお越しいただいて、ありがとうございます」
と続き自己紹介をした。
シュンたちも
「初めてお目にかかります」
と少し緊張しながら挨拶をし、自己紹介をした。
その後シュンのおじいちゃんも挨拶をした。
「今回おじゃまさせていただいた孫の沢木俊一の祖父に当たる沢木健吾と申します。実は私は、今から50年ほど前に、一度みなさんにお会いしたことがあります」
おじいちゃんがそう言うと、3人は意外そうな顔をして互いの顔を見合わした。
「さて、どこでお会いしたのでしょうか」
トシヒデさんが、不思議そうな顔をして言った。
「はい、あの鹿島小学校の閉校式の会場でです。私は、あそこの生徒で、小学3年でした」
すると、トシヒデさんたち3人は、驚きの声を上げ、やや緊張気味な雰囲気が一気に打ち解けたものになった。そして、おじいちゃんの話に耳を傾けていた。
おじいちゃんは、あの日3人に頼まれて、カメラのシャッターを押したこと。また、3人で一緒に写真を撮ってもらい、アキオさんにその写真を送ってもらったことなどを話した。
おじいちゃんは、そのときの写真をカバンから取り出し、三人の前に出した。
「あらっ、懐かしいわね。この写真のことは良く覚えていますよ。良く持ってきてくださいましたね。ありがとうございます」
ミヨコさんは写真を手にすると愛おしそうに眺め、名残惜しそうにアキオさんに渡した。
「この写真、今でも私のアルバムに大切に取ってありますよ。でも、三人とも若いですね。まだ、40代の前半あたりですか。沢木さん、この写真をお持ちいただき本当にありがとうございます」
アキオさんはそう言うと、おじいちゃんに深々と頭を下げ、写真をトシヒデさんに渡した。
「この小学生の方が、沢木さんなんですね。しかし、不思議な縁ですね。あのとき一緒に写真を撮らせていただいた沢木さんのお孫さんが、そのタイムカプセルを掘り出してくれたのですから」
アキオさんは、車椅子の上でそう言いながら、何度もうなずいていた。
「夏休みに、僕たち偶然あのカエデの木の下で、テントを張ってキャンプをしたんですよ。そしてその夜から何度か、昔の3人の中学生がタイムカプセルを埋める夢を何度も見て、僕だけではなく、この2人も同じ夢を何度も見て」
とシュンが言った。
「あのカエデの木は、樹齢が300年近いそうです。木も古いものになると、その土地の神様が宿るそうです。だから、偶然あそこでキャンプをしたシュンたちが夢を見ることになったのかもしれません。私はそんな気がしています」
シュンの母もゆっくりとアキオさんたちに言った。
「私たちも、あのタイムカプセルのことは、いつも気になっていました。一度だけ3人で掘り起こしに行ったことがあるんですよ。そう、あの鹿島小学校の閉校式の翌日でした。閉山後誰も訪れる人がいなかったのでしょうね。うっそうと草木が生い茂っていてどの木も、大きくなっていて、あの場所が見つからなかったのですよ。結局時間もなく、諦めて帰りましたよ」
トシヒデさんはいかにも残念そうに言った。
3人は、地元の高校を卒業すると、進学や就職で街から出た。ところが、その翌年炭鉱は閉山になり、帰ってくる家もなくなってしまった。その後3人が一緒に帰ることができたのは、鹿島小学校の閉校式の時であった。
「あんなにも早く閉山するなんて思ってもいなかったんですよ。そりゃ、早く狭い街を出たいとは思っていましたよ。でもそれは、いつでも帰ってこれるという、どこかで安心している気持ちがあったからなんですよ。それが、急になくなってしまうなんて・・・」
トシヒデさんが溜息をつくように言った。
「親も兄弟も友達もみんないなくなってしまった後は、帰るといっても、中々帰ることができなくてね」
ミヨコさんも、しみじみと言った。
「だから、その、タイムカプセルも掘り出しに行けなくてね。 でも、あの場所に私たち3人の思い出が埋まっているという、何ていうかその事実があるだけで、ずっと故郷と繋がっているような気がしてね。 だから、まだ若かった頃、いつか掘り出してやるという目標が、一つの私たちと故郷の約束のような気がしてね」
アキオさんも思いを込めるように言った。
(帰る場所がなくなっても、タイムカプセルが、アキオさんたちと故郷を結び付けていた)
シュンたちも、そんな3人の気持ちが、わかるような気がした。
「そんな思いで、時が過ぎて行く中、もう40代に入った頃に、鹿島小学校の閉校式のことを知ったんですよ。そして思ったんですね。掘り起こすなら今しかないと」
ミヨコさんが言った。
「でもね、見つけることができなくてね。それを、あのとき一緒に写真を撮った沢木さんのお孫さんたちが、掘り出してくれたんですから、本当にありがたいことです」
トシヒデさんは、シュンたちに手を合わせて言った。
「何ですなあ、その、タイムカプセル早いとこ見たいものですなあ」
アキオさんが少し照れながら言った。
「全く、年寄りはせっかちなんだから。でも、私も早く見たいですけど」
ミヨコさんそう言うと、みんなもつられて笑い出した。
シュンはバックの中から、タイムカプセルを取り出した。
リョウとヒデも1個ずつ手にした。そして、シュンたちは、ミヨコさんたち3人にそれぞれ渡した。
「あの、タッパウエアーだ」
アキオさんは車椅子の上で踊り上がるようにして、受け取った。そして3人は、ふたを開ける前に、シュンたち1人1人の顔をしっかりと見て
「本当にありがとうね。まさか、生きているうちに手にすることができるとは思っていなかったわ。本当にありがとうね」
と言いながら、感極まって少し涙を浮かべていた。
3人は、それぞれの思いを胸にふたを開けた。
夢に出てきたあの中学生たちが、こうして年を取って、また3人揃って約束どおりタイムカプセルを手にしている光景を目の前で見ていると、シュンたちもそのタイムカプセルに引き込まれていくようであった。
このタイムカプセルとの出会いが、シュン、リョウ、ヒデの3人を思いかけず、大夕張という大きな歴史の流れと出会うことができた。もう大夕張は、シュンたちにとっては、単なる生活の場ではなく、大切な大地になっていた。
(俺たちは、この3人と繋がっているんだ)
シュンたちはそんな思いを込め、タイムカプセルを手にしている3人を見ていた。
「あら、あんたたち、あんなに言ったのに手紙にあのときの日付書いてないんだから、全く」
ミヨコさんは二人に言っていた。
それを聞いてシュンたちは顔を見合わせて笑い出した。そして皆も笑い出した。
この夏休みのことは、シュンたち3人も「思い出」というタイムカプセルに永遠に残しておこうと思った。
~終わり~
西暦2050年,新エネルギー革命により原野に新しい街が生まれる。街の名は,大夕張と呼ばれていた。
(2009年発表)
(作者紹介)
夕張市鹿島生まれ
生まれてから高校卒業までの18年間を大夕張で過ごす。『ふるさと大夕張』にはしばしば投稿していたようだが、素顔は謎である。札幌在住。